「自分でやりたい!」と主張するようになった子どもの対応方法に迷っていませんか?
1歳ごろから始まる「やりたい」気持ちは、子どもの自我や主体性の芽生えのサインです。
本記事では、子どもの「やりたい!」を応援する親の関わり方を4つ紹介します。
子どもの成長を優しく見守るヒントがきっと見つかりますよ。
「自分でやりたい」の始まりはいつ?
1歳ごろからの自我の芽生え
1歳になり、歩き始めたり言葉を使うようになったりすると、身の回りのものや身近な人に自分から関わろうとします。
子どもは、様々な動きができるようになっていく中で自信を持ち、意欲を高めていきます。
つまり、「じぶんでやりたい」という自我が芽生える時期なのです。
子どもが「やりたい!」と主張するのは、自我が順調に育っている証拠とも言えます。
やるやる期とイヤイヤ期の違いは?
子どもは「やりたい!」と思ったことがうまくできずに、イライラしたり葛藤したりします。言葉でうまく伝えられればよいですが、まだ言葉も発達途中。
「もうどうしたらいいの!?」という気持ちが爆発した状態、それがイヤイヤ期です。
よく、子どもがやりたいという時期を「やるやる期」と言いますが、このやるやる期とイヤイヤ期は重なることが多いです。
「やりたい!」ことはあるけれど、自我の芽生え真っ最中の子どもは「やりたくない!」ことももちろんあります。また、やりたいことがうまくできない場面もしょっちゅうあります。
そのため、自然とイヤイヤ期と重なるのです。
「やりたい」気持ちを大切にすると主体性が伸びる
子どものやりたい気持ちは、主体性を育てる上でも大切です。
「好き」「興味がある」という気持ちから行うことは、意欲的に取り組めます。誰かに言われてやるよりも子ども自身の力もぐんと伸びますよ。
「自分で考える力」や「問題を解決する力」が育ち、「できたという達成感」が自信につながっていきます。
子どもが「やりたい」と思ってしたことは、子どもの主体的に考える力を伸ばすことに繋がるため、大事だと覚えておきましょう。
子どもの「やりたい!」気持ちを応援する4つの関わり方
子どものやりたい気持ちを応援するための関わり方は、以下の4つです。
- やりたいができる環境を整える
- やり終えるまで見守る
- できたら認める・褒める
- 甘えは受け止める
関わり方を知って、子どもの「やりたい!」を存分に尊重してあげましょう。
「やりたい」ができる環境を整える
子どもがやりたいと思ったことができる環境を整えることが大切です。
子どもが少し頑張ればできる環境にすると、やりたいことができて達成感が味わえる上に、自己肯定感も高められます。
例えば、子どもがお茶を自分でコップに「ジャー」と注ぎたいと言ったとき。親であれば、「まだ難しい」「こぼされたくない」と思ってしまうかもしれません。
そんなときは大人が視点を変えて、子どもができるよう入れ物やお茶の量を調整してください。
なんでもやってあげるのではなく、子どもが少し頑張ってできる環境に整えるだけで、「やりたい」気持ちを尊重できますよ。
ただし、危険が伴うことは介入しましょう。
「これは危ないからできないよ。でもこうすれば安全だから・・・」と代替案を用意すると子どもも納得しやすいため、おすすめです。
やり終えるまで見守る
子どもがやりたいと思ったことをやり終えるまでは、見守るようにしましょう。
大人がよかれと思って手助けしてしまうと、子どもが癇癪を起す原因になる恐れがあります。
たとえば、靴を履く場面で、子どもはマジックテープを剥がして足を入れようと思っていたとします。
そこで大人が「ベロの部分も上に持ち上げると履きやすいよ。」と手助けしてしまうと、子どもは「自分のやり方があるのに!」となってしまうのです。
子どもが自分で頑張っているときはそっと見守るのでOK。
時間がかかる場合があるので、大人は余裕をもっておくとよいですね。
できたら認める・褒める
子どもがやりきったときには、言葉にして認める、または褒めてください。
大好きなママやパパに褒められたことで、自信となり次の意欲へ繋がります。
また、自分でやりきった満足感も得られるのです。
声掛けのポイントは、「すごいね!」「えらいね!」ではなく、事実やできた過程を褒めるとよいです。
「自分で靴を履けたね!」
「1人で頑張ったんだね!」
できた結果を褒めるのではなく過程を褒めることで、今後失敗を恐れずに挑戦する気持ちも育めます。
子どもがやりきった瞬間を見逃さず、一緒に喜んであげましょう。
甘えは受け止める
「やりたい!」主張が激しい子でも、時には甘えたくなるもの。
子どもが甘えてきたときは、受け止めます。
大人でもやりたくないなって時がありますよね。子どもも同じです。
そんなときに、大好きな人が気持ちを受け止めてくれるだけで、「次はやってみようかな」と思えるのです。
いつもなら自分でやっていることも、「ママやって」と言われたらやってあげましょう。
やってあげることで子どもの自立の妨げにはなりません。
むしろ、大人への信頼感が育ち、「かっこいいところを見せたい!」と頑張るようになりますよ。
やりたい時期の子どもでも、甘えてきたときは存分に気持ちを受け止めて、代わりにやってあげるのも大切です。
応援するときのポイント
子どもの応援をするときのポイントは2つあります。
- 「できた」ではなく「やってみたい」を大切に
- 忙しいときは無理をしない
ポイントを理解し、無理なく子どものやりたい気持ちを応援しましょう。
「できた」ではなく「やってみたい」を大切に
「できた」「できない」ではなく、「やってみたい」「やってみよう」という意欲を大切にしてください。
つい、子どもが挑戦していると結果に目を向けがちになってしまいますが、大人が結果だけを見ていると、子どもは失敗を恐れるようになります。
できてもできなくても、「やってみたい」と思って挑戦した気持ちに目を向けることで、子どもは結果にこだわらずにどんどん取り組みます。
忙しいときは無理をしない
忙しいときは無理をしないのも、子どもを応援するときのポイントです。
ときには忙しくて、子どもがやりたがっていたことをやってしまっても大丈夫。イライラして、向き合えなくても自分を責めないでください。
気持ちが落ち着いたら、子どものしようとしたことを認めてあげるだけでOKです。
「時間がなくてやってしまったけど、〇〇しようとしていたよね。」
「頑張っていたよね。」
と伝えてハグしましょう。
まとめ:子どもの「やりたい」を未来に繋げよう
子どものやりたい気持ちは、主体性を育む上でも大切です。
誰かに言われてやるよりも、自分でやりたいと思ってやることの方が子どもの力をぐんと伸ばします。
そのために大人は、環境を整え頑張る姿を見守ったり、できたときには一緒に喜んだり・・・
時には甘えを受け止めながら、子どもの「やりたい」気持ちを尊重する関わりを心がけてみてください。
ママやパパも人間ですから、やりたいを聞いてあげられないときもあります。
そんなときは、お話してぎゅっとハグするだけでOK。無理はしないことも大切ですよ。
子どものやりたい気持ちを応援して、未来を生きる力を一緒に育んでいきましょうね!
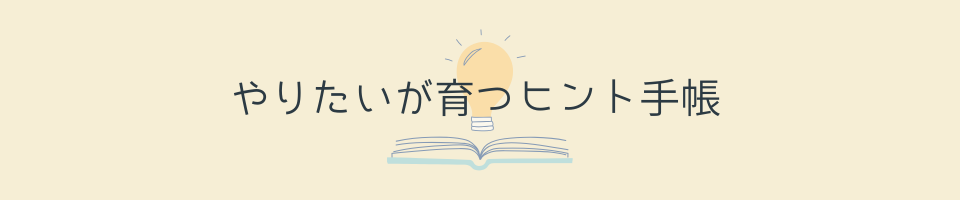

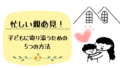

コメント