子どものイヤイヤ期が始まり、「どうしたらよいかわからない」と関わり方に悩んではいませんか?
「毎日イヤイヤされて大変!」と、イヤイヤ期は親にとって試練の時期であることが多くあります。
でも実は、子どもの“主体性”が育ち始めているサインでもあることを知っていますか?
本記事では、イライラしがちなイヤイヤ期を前向きに乗り越えるためのヒントと、子どもの主体性を育てる関わり方をお伝えします。
イヤイヤ期とは?
イヤイヤ期とはどういうものなのでしょうか。
- どんな時期なのか
- なぜ起こるのか
- 視点を変える大切さ
3つのポイントを押さえて、イヤイヤ期についてしっかりと理解しましょう。
イヤイヤ期について知ると、対応するときに気持ちがグッと楽になりますよ!
イヤイヤ期とはどんな時期?
イヤイヤ期とは、主に1歳半ごろから始まります。「自分でやりたい!」「これはやりたくない」などと、自己主張が始まったサインでもあります。
ピークは2歳ごろで、イヤイヤ期が落ち着いてくるのは4歳ごろが多いです。言葉で自分の気持ちをうまく伝えられるようになると落ち着きます。
なぜ起こるの?
イヤイヤ期が始まるころの子どもはまだ我慢する力がありません。うまくいかなかったとき、自分の感情との向き合い方を知らないため、「イヤ!」と全身で表現します。
子どものイヤイヤが起こる具体的な場面には、いくつかのパターンがあります。
まずは、やりたいことがうまくできなかったとき。
周りにできなかったことを伝えられなかったり、できなかったときの葛藤を感じたりすることから反発が起きます。
次に、自分の秩序が崩されたとき。
子どもにとって、やることに順序が決まっている場合があります。大人がよかれと思って先回りしてやってしまうと、「自分のやり方でやりたいのに!」と癇癪に繋がることもあるのです。
子どもにとってままならないことがあったとき、言葉で表現できないため、イヤイヤが起こると覚えておきましょう。
「困った」ではなく「成長の証」と見る!
親にとっては「困る」イヤイヤ期。ですが、「成長の証」と見ると子どもへの接し方も変わります。
イヤイヤ期は子どもの自我が芽生えた証拠です。ここから子どもは、自分で考え行動する力を育んでいきます。また、嫌な気持ちを受け止めてもらい、自分の感情のコントロールの仕方を学ぶのです。
この時期に大人が丁寧に関わっていくことで、子どもは自分で考える力を育み、周りの人ともうまく関わっていけるようになります。人生において大切な「生きる力」の土台を築く時期ともいえるでしょう。
主体性を伸ばす!イヤイヤ期の子どもへの接し方
イヤイヤ期の子どもの接し方は4つあります。
- 子どもの気持ちを受け止める
- 気持ちの切り替えを手伝う
- 冷静に対応する
- ダメと言わなくてよい環境を作る
子どもに「自分で考える」「自分で決める」場面を増やすと、主体性を伸ばすことに繋がります。ぜひ参考にしてください。
子どもの気持ちを受け止める
イヤイヤ期の子どもの接し方の1つは、「イヤ」という気持ちを受け止めることです。
まだ、自分の気持ちを言葉で伝えられないため、大人が嫌なことを汲み取り代弁してあげましょう。
たとえば、靴が履きたいのにうまく履けなかったときに、子どもが泣くのであれば「悔しかったね。」と声を掛けます。嫌だった気持ちをわかってもらえるだけでも子どもは安心できます。
「どうしたい?」と聞くのもよいでしょう。
子どもが身振りや簡単な言葉で意思を伝えてきたときには、「じゃあ、こうしてみようか。」や「手伝ってほしい時は手伝ってって言うのよ。」と対応方法を教えると、子どもが自分の気持ちのコントロールの仕方を学ぶことに繋がります。
子どもが「手伝って」と言えるようになったときは、大きな一歩です。自分の思いを言葉にして表現する経験を繰り返すことで、自己決定力も少しずつ育っていきますよ。
気持ちの切り替えを手伝う
子どもがイヤイヤと癇癪を起すときには、気持ちの切り替えを手伝いましょう。場所を変えたり、違う遊びに気をそらすと、子どもの気分を変えるサポートができます。
室内でイヤイヤが起こり泣き続けるときは、外へ出ることをおすすめします。
泣く時間が長くなると、子ども自身も何が嫌だったのか分からなくなってしまうもの。
そんなときには「〇〇が嫌だったんだね。じゃあ少し外の風を浴びて気分を変えようか。」と環境を変えてみるだけでも、子どもが落ち着く場合があります。
関わりの中で気持ちの切り替え方を学んでいくと、今後うまくいかないときにも挫けずに次へ進む力が育ちますよ。
冷静に対応する
子どものイヤイヤには冷静な対応を心がけてください。
イヤイヤ期の子どもの主張は、大人にとっては理不尽に感じたり理解できなかったりする場合がありますが、感情的にならずに落ち着いて関わることが大切です。
子どもは大人の反応をよく見ています。親が穏やかに対応すると、「気持ちは受け止めてもらえるんだ」と安心し、気持ちが落ち着くきっかけになります。
また、親が冷静な姿でいることで、子どもにとっては感情のコントロールのお手本にもなります。
大変な時期ではありますが、「あなたの気持ちはわかるよ」と共感しながら関わることが、子どもの主体性を育てる第一歩になります。
ダメと言わなくてよい環境を作る
ダメと言わなくてよい環境を作ることも、イヤイヤ期の子どもの接し方の1つです。
子どもは好奇心の塊です。気になったものは何でも触りたくなるもの。大人にはいたずらに見えることも、子どもにとっては「どうなるのかな?」と学んでいる場面でもあるのです。そんな好奇心からやってみたことを止められたときに、子どもがどうなるかはわかりますよね。
しかし、大人にも触ってほしくないものはあるものです。
そのため、子どもに触ってほしくないものはあらかじめしまっておいたり、開けられないようロックをしたりして、「ダメ!」と言わなくて済む環境を整えましょう。
子どもが「やっていいこと」が多い環境では、自然と自分で判断する経験が増えます。判断の積み重ねが、主体性の芽を育てていくため、子どもにとってよい環境を作ることが大切になります。
子どものイヤイヤと向き合う3つのコツ
子どものイヤイヤと向き合うために、3つのコツがあります。
- 他と比べない
- 周りを気にしすぎない
- 余裕がない時は一歩引く
育児をする上では、ママやパパの余裕が子どもにとってよい影響を与えます。
コツを知り、子どものイヤイヤにも無理なく付き合いましょう。
他と比べない
イヤイヤと向き合うコツは、他と比べないことです。
他と比べてしまうと、「子どもにうまく対応できていない自分がおかしいんだ」と余計に辛くなってしまう場合があります。
今はSNSで、気軽に他の家庭の育児の様子を知ることのできる時代です。
同じ年齢の子でも「イヤイヤがない」「話せば聞いてくれた」など、目の前の我が子とは全く違う様子が目に入ることもあるでしょう。
子どもの発達や成長は、それぞれであり個人差も大きいものです。イヤイヤ期が始まる1歳半ごろは特に個人差が大きい時期です。
SNSや人から話されることが全てではないと理解し、比べないよう気をつけてください。
周りを気にしすぎない
周りを気にしすぎないのも、イヤイヤ期と向き合うコツです。
外出時に、子どもが癇癪をしたときは周りからの目が気になると思います。責任感の強い方であれば、「周りに迷惑をかけてはいけない」と子どもにも言い聞かせようとしてしまうのではないでしょうか。
しかし、子どものイヤイヤは成長の過程であり、ほとんどの子が通る道です。
道で寝転がったり、大きな声で泣くかもしれませんが、子どもが意思を主張することはいけないことではありません。また、「イヤイヤを起こさせてしまった」と親が申し訳なく思う必要もありません。
どうしても周りの目を引くかもしれませんが、子どもの成長過程であることを頭に置き、気にしないよう心がけましょう。
そうはいっても、気になってしまうものですよね。そんなときは無理せずに「そうだね、嫌だよね。」と気持ちを受け止めながら場所を変えましょう。
子どもの気持ちを切り替えてしまうのも1つの手ですよ。
余裕がない時は一歩引く
子どものイヤイヤ期はすぐに終わるものではないため、余裕がない時は一歩引くことも、向き合っていくコツになります。
今は無理かもと思ったら、「今は悲しい気持ちだから、少し向こうに行くね。」と声をかけて安全を確保し、一旦子どもから離れましょう。
ママやパパも人間ですから、成長の過程だと思っていても向き合えないときもあります。
気持ちが落ち着いたら、子どもの気持ちを受け止めてぎゅっとしてあげるのでOKです。
子どものイヤイヤを「うまく乗り越えさせなきゃ」と思うと親も疲れてしまいます。
親が少し力を抜いて見守ることで、子どもも「自分の気持ちは自分で整理していいんだ」と気づき、心の主体性を育てていけますよ。
余裕がない時はそっと離れて、少し離れた場所で子どもの様子を見守りましょう。
まとめ:大変なイヤイヤ期は見方を変えて関わろう!
子育ての中では特に大変に感じる時期であるイヤイヤ期。ですが、見方を変えてみると「困った行動」も「成長の一歩」に思えてくるかもしれません。
そんな大変な時期も、子どもにとっては自我が芽生え始めて、自分という「個」を確立しようとしている大切な時です。
気持ちを受け止めたり、気持ちの切り替えを手伝ったりすることで、子どもの主体性を育むことができますよ。
ただし、イヤイヤ期は親にとって辛く感じることもあるものです。無理のない関わり方を見つけて、子どもの成長の過程を見守っていきましょうね。
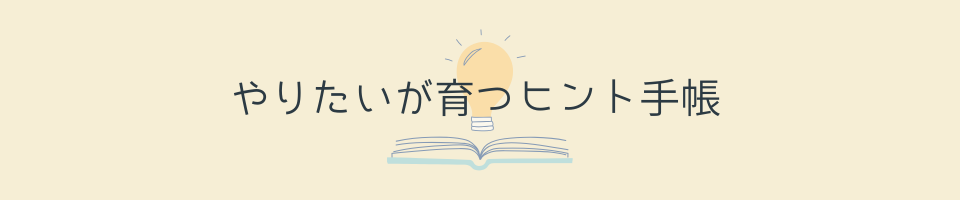
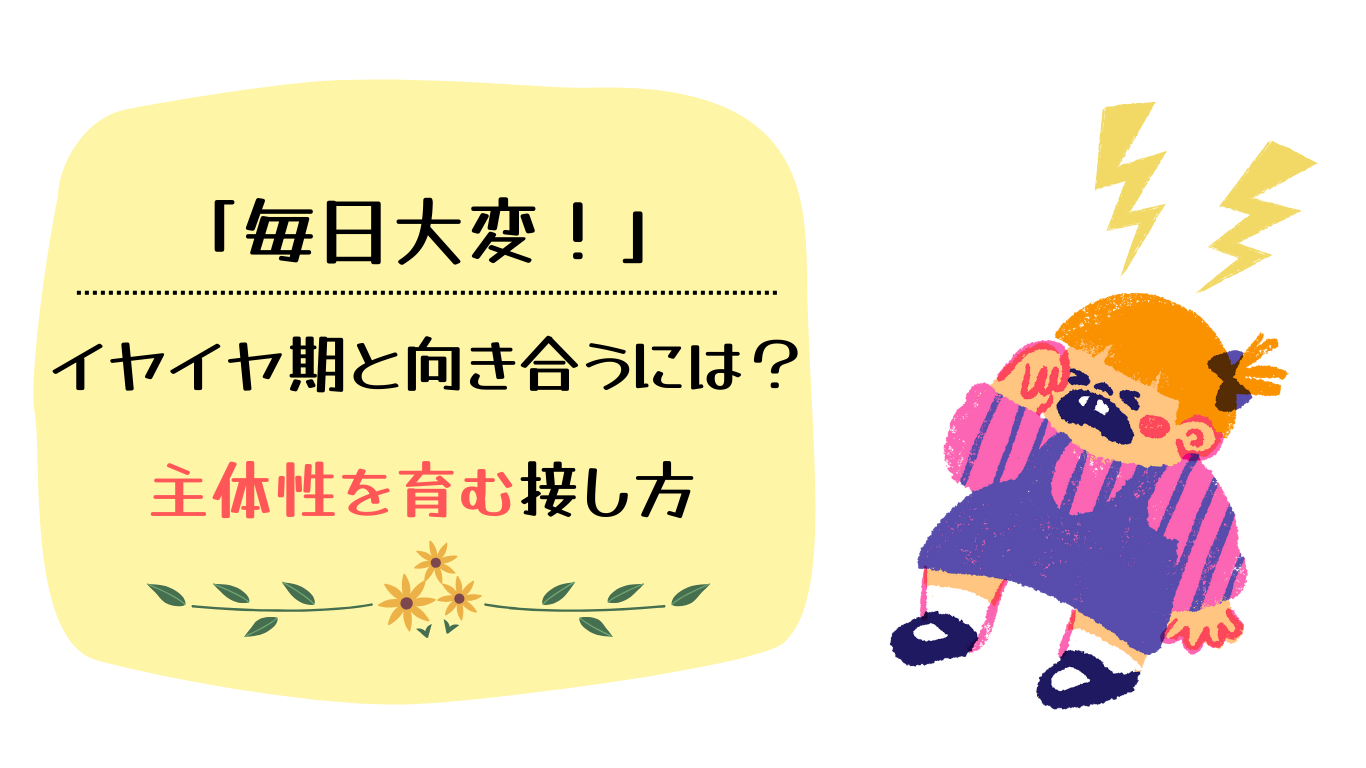


コメント