「保育の余白」という言葉を聞いたことがありますか?
保育の余白とは、時間や空間的なゆとりを持ち、子どもが安心して自由に遊べる時間のことです。
毎日保育をしていると感じることがあります。
それは「なんかバタバタしているなー!」
天気がいいと園庭や公園で遊んでもらいたいと、つい計画してしまいませんか?
しかし、公園へ行くには子どもを誘って、排泄を済ませてとやることはたくさん。
一人ひとりに声を掛けるものの、スムーズにいくかどうかは子どもによって違います。
公園に行くためにやることをやっていると、時間はあっという間に過ぎていきます。
また、公園へ行っても、遊べる時間には制限がありますよね。
そうしてバタバタしているうちに給食や午睡の時間になり・・・。
保育をしていると、子どもが時間を気にすることなく、遊べている時間がどれくらいあるだろうと考えてしまいます。
もっと余裕を持って保育がしたい。時間に追われて子どもとの関わりが雑になるようなことは避けたい。
そう思ったときに出会ったのが、「保育の余白」という言葉でした。
余白を作ると、子どもが主体的に動くことに繋がるそうです。
今回は、「保育の余白」について調べたことや感じたことを私なりにまとめて紹介します。
同じように時間に追われて、子どもと丁寧に関われていない気がすると悩む方のヒントになれば嬉しいです。
保育の余白とは?
保育の余白とは、時間や空間のゆとりを指します。
目的は、子どもが自分で考えて動く時間を保障すること。
子どもが自分から「やってみたい」と思って動くには、考えるための時間や、選べる余地が必要です。この余白があることで、大人の指示ではなく、子ども自身の意思で行動できるようになります。
つまり、余白は子どもが主体的に動くための「きっかけ」や「土台」となるのです。
保育の余白を作るための2つの工夫
1.環境を作りこまない
保育に余白を作るためには、環境を作りこまないことが大切です。
「こうなってほしい」「ああしてほしい」と保育者の思いを環境に強く反映させると、子どもが思いを汲み取って動いてしまう可能性があります。
そのため、あえて環境設定は完璧にしないことがおすすめです。
たとえば、製作物の素材を用意する際、1つのものを用意するのではなく、様々な種類を用意して子どもが選べるようにします。
完璧な状態ではなく、余白をあえて作ると子どもが考えることにつながります。
環境を作りこまず、子どもの自由な発想を楽しみましょう。
2.時間にゆとりを持つ
時間にゆとりを持つと、保育の余白を作れます。何もない時間が子どもの興味ややりたいことを見つける時間になります。
つい、保育の計画を立てるときに時間いっぱいまで活動をしないといけないと思ってはいませんか?
子どもが退屈してしまうかも、と心配になるかもしれませんが、時間の余裕こそが子どもが何かを自分で決める機会を生みます。
余白を作って、子どもが「何をしよう?」「こうしてみたい」という気持ちが自然に湧くようにし、子ども自身の意思で動く力を育てていきましょう。
余白が大切だと感じたエピソード
私が保育の余白について調べたのは、時間に追われて自分の保育に余裕がなく、「じっくり子どもと関われているだろうか」と疑問に思ったからです。
私が働いている中で、朝のおやつの時間に起きたことです。
車で遊んでいる男の子に、おやつが来たから食べに行こうと誘いました。
男の子は遊びに集中しており、「やだ」と言われてしまいました。
おやつの後は散歩の予定があったのと、おやつの時間も限られているため何度か誘いましたが、断られ続け…
もう食べたくないなら仕方ないか、と半ば諦めて誘うのを一度やめました。
すると、満足するまで遊んだら「おやつ、食べる」と言って自分から手洗いをし、おやつを食べに来たのです。
こちらがどうにかしようとしなくても、子どもは自分で区切りをつけて活動に参加できることがわかった出来事でした。
また、時間に余裕があれば、子どもが自分から動くのを待ってあげられるのに、とも思いました。
今回の件は遊びではありませんが、余白の必要性を感じました。
余白のある保育実現するために必要なこと
では、余白のある保育を目指すためには、どうしたらよいのでしょうか。
私は、時間と保育士の気持ちのゆとりが必須だと感じました。
保育では、日々計画を立てて子どもの様子に合わせて時間を設定しますよね。
しかし、余白のある保育をするためには、綿密な時間設定こそ大きな壁になってしまいます。
「子どもに楽しんでもらいたい」
「何もしない時間があるとつまらないのではないか」
子どもを思うがゆえに、つい何かをしないといけない気持ちに駆られてしまうのも、保育士あるあるではないでしょうか。
ただ、めいいっぱい詰め込まれたスケジュールでは、子ども側から「何かしたい」「やってみたい」という気持ちが生まれづらいのも事実です。
すべてが用意されている環境では、それをやるしかありませんからね。
そのため保育士は、「子どものために何かをしなければ」という思いを少し手放してみる。
また、ゆとりを持った時間設定で計画を立てる。
子どもが好奇心や興味から動く様子があれば計画を変更してでも見守れる、そんな保育を目指したいですね。
おわりに:保育に余白を持つことは「サボり」ではない!
余白は、手を抜くことではなく、子どもが自ら動くための準備時間だと思います。
すべてを変えることは難しいため、まずはできるところから少しずつ変えていくのも1つの手です。
たとえば、活動までの時間を少し長めにとることや、自分の思いが詰まった環境を見直してみるなど。
ほんの少しでも「余白」を持ってみることをおすすめします。
保育の余白は、子どもが動き出すための出発点です。私たちが少し手を引くことで、子ども自身が前に出てくる。そんな関わりが、主体性を育む第一歩だと感じます。
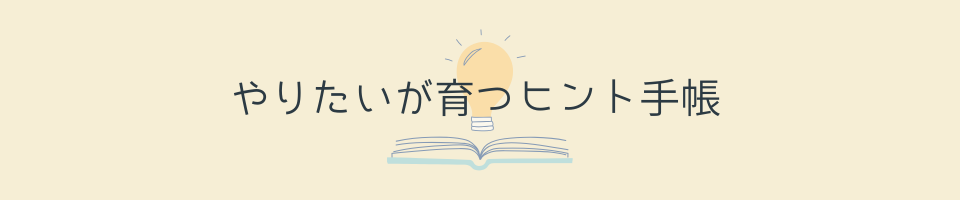
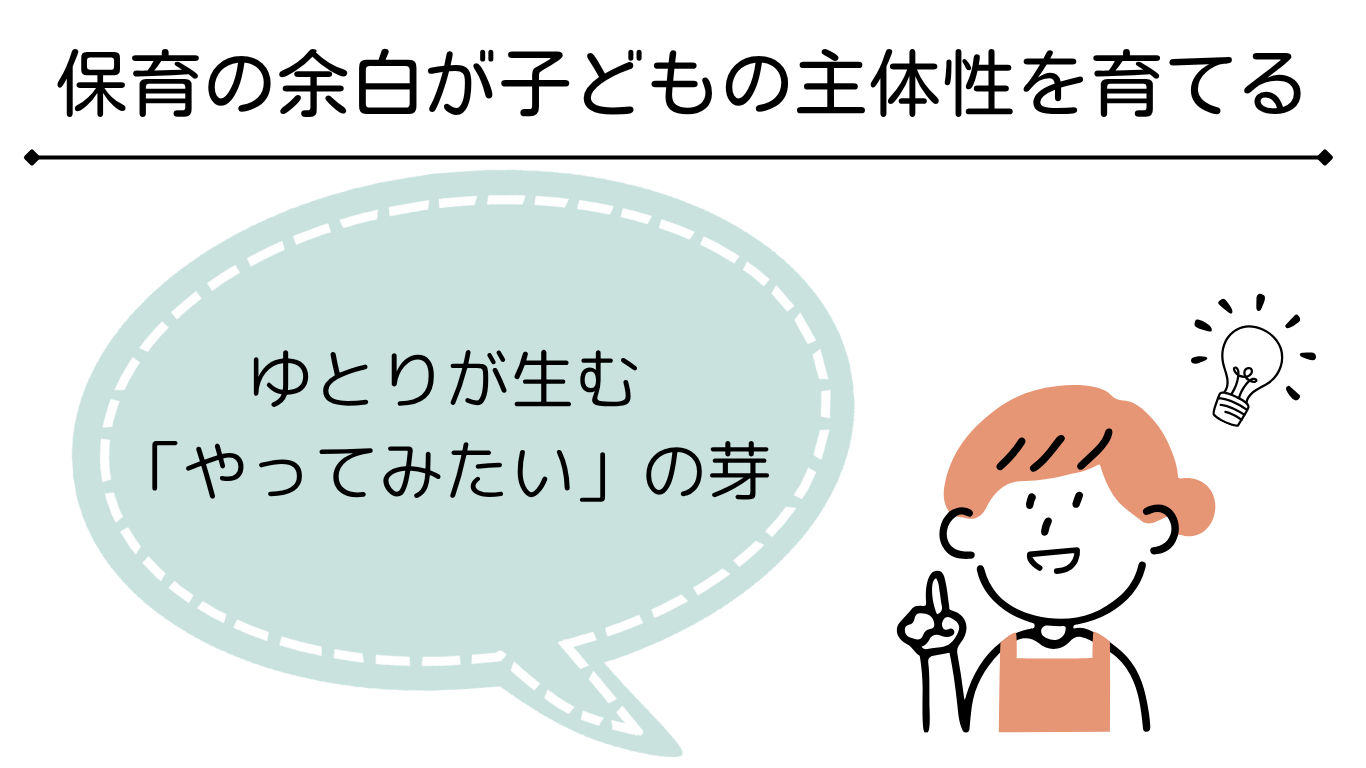
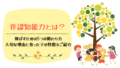
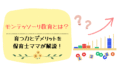
コメント