子育てにおいて、子どものペースに合わせて見守ることが大切であるという話は、誰しもが1回は聞いたことがあるのではないでしょうか。
「子どもを待つことが大事という話は聞くけれど、仕事をしていると難しい」
「どうしても時間がなくて急かしてしまう」
そう悩む保護者の方に向けて、
- 「待つ」ことが大事な理由
- 子どもを待つためのコツ
- 待てないときの対処法
をわかりやすくご紹介します。
忙しくても子どもに寄り添う気持ちを大切にしたいと考えるママ・パパにとって参考になれば嬉しいです!
子どもを「待つ」ことが大切な理由
子どもを「待つ」ことが大切な理由はいくつかあります。
- 自分で考えてできるようになる
- 自己肯定感が高まる
- 忍耐力がつく
なぜ「待つ」ことが大事なのかを知り、明日からの子育ての参考にしてください。
自分で考えて行動できるようになる
子どもを待つと、自分で考えて行動できるようになります。自分のやりたいことに取り組み、苦戦しながらも試行錯誤して達成しようとする経験ができるからです。
逆に親の都合で子どもが挑戦していることにアドバイスをしたり、手助けをしたりすると考えなくてもできてしまうため、指示を待つようになってしまいます。
大人は経験があるため、効率的な方法を教えたくなりますが、我慢して子どもが頑張っているのを待ちましょう。
将来、困難に出会っても自分の力で解決できる力が育ちますよ。
自己肯定感が高まる
子どもを待つことで、自己肯定感も高まります。自分がやりたいことをママやパパが見守ってくれているとわかると、「自分は尊重されている」と感じるのです。
また、待ってもらうことで、子どもは「自分でできた」という経験を重ねられ、達成感を得られます。
日々の経験の積み重ねが子どもの自信となり、生きる上で最も大切な「自分自身が存在しているだけで価値がある」という自己肯定感へ繋がっていきます。
自己肯定感が高まると、子どもは新しいことにも挑戦しやすくなりますよ。「やってみよう」と思える気持ちが芽生えることで、学びや成長の機会も広がります。
自己肯定感の有無で、人生の生きやすさは大きく変わります。子どもが将来生きていきやすいように、子どもを待つことを大切にしましょう。
忍耐力がつく
待ってもらった経験がある子どもは、他者に対しても「待つ」ことができます。また、公共の場で我慢しなければいけない場面でも、落ち着いて行動できる忍耐力が育ちます。
自分が待ってもらったことで感じた「安心感」や「信頼されている」という実感が、子どもの心の中に余裕を生み、他人にも同じように思いやりを持って接する土台となるのです。
忍耐力は簡単に身につくものではありません。しかし、日々の「待つ」関わりの積み重ねで、少しずつ子どもの中に芽生えていきますよ。
子どもを「待つ」ためのコツ
時間には余裕を持つ
子どもを待つためには、時間に余裕を持ちましょう。ただ、お仕事をされている方にとっては、時間に余裕を持つこと自体が難しいときもあると思います。
そのため、例えば子どもがやることには10分以上はかかると考えて、その分だけ時間に余裕を持たせておくというのも手です。
衣服や靴の着脱を自分でやりたがる子がいるならば、どれくらいかかるか把握したうえで、必要な時間分のみとっていくということです。
私の子どもも、現在「何でもやりたい!」期なので、30分は時間に余裕を持たせていますよ。
時間に余裕を持って、子どもを「待つ」ための心のゆとりを持つことをおすすめします。
見通しが持てるようにする
子どもを待つコツとして、見通しを持たせることも大切です。見通しが持てるようになれば、子どもが自主的に動いてくれるため、「待つ」こと自体も減る可能性がありますよ。
たとえば、朝の忙しい時間に遊び始めたときは「タイマーが鳴ったらおしまいにしようね。」と声をかけて時間を区切ります。
また、「着替えたら、ごはんを食べようね。」と次の行動を伝えることでも、子どもは見通しを持てます。
時計がわかるのであれば、「〇分にごはん」「〇分に出発」などタイムスケジュールを書いて、見える場所に貼るのもよいでしょう。
はじめは上手くいかないかもしれませんが、次第に子どもがわかるようになってくれば、待つことも少なくて済みます。
子どもが自主的に動くようになるまで、根気強く伝えていくのが重要です。
声掛けを工夫する
声掛けを工夫すると、子どもを待つ時間が短くなります。
子どもを急かすのではなく、「どうしたらうまくいくかな?」と解決の手がかりになるような声掛けをすると、子どもが自分で考える力が身につきます。
その経験を繰り返し、自分で考えて行動できるようになると結果的に待つ時間も少なくなり、イライラもしません。
声掛けを工夫して子どもの考える力を育み、「待つ」時間を減らしましょう。
どうしても待てないときの対処法
自分の気持ちを認めてあげる
どうしても待てないときは、自分の気持ちを認めてください。
「今は、待てないときなんだな」と受け止めると、冷静になり、子どもを再び落ち着いて関われます。
ママやパパも人間ですから、イライラしてしまうもの。仕事と育児を両立されていると余計に心の余裕もなくなりがちです。
余裕がない時は「そういうとき」と自分の気持ちを認めて、完ぺきを目指さずにできる関わりをしましょう。
全部ではなく1つだけ「待つ」
全部ではなく1つだけ待つことも、待てないときの対処法の1つです。
どうしても時間のない時や、余裕がなくて待てない時は、どれか1つだけ待ってあげるようにします。
たとえば、衣服の着脱は手伝ってしまうけれど、靴を履くのは待つということです。
子どものしたいことをすべて奪わずに済むため、意欲や達成感を損ないにくくなります。
1つだけの「待つ」かもしれませんが、小さな積み重ねでも子どもは自信をつけていきますよ。
「待つ」日を決める
どうしても待てないときは、待つ日を決めることをおすすめします。
あらかじめ決めておくと、心にも余裕が出て子どもをしっかりと見守ることができます。
子どもにとっては、「待つ日」と「待ってくれない日」が出てきて混乱することもあるかもしれません。
しかし、「今日はどうしても遅れられないから、お手伝いするね。」とその都度理由を話していけば、子どもも次第に納得してくれます。
理解するまでは気持ちの切り替えが難しいこともあるかもしれませんが、丁寧に伝えていきましょう。
まとめ:工夫して子どもを待ち、大切な力を育もう
子どもがやりたいことを待つと、自分で考えて動ける力が身についたり、他者にたいして待てるようになったりと、生きていくうえで大切な力が育ちます。
また、待ってもらった経験から、「自分は大切にされている」と感じて、自己肯定感も高まります。
しかし、仕事をしていると気持ちに余裕がなくなり、子どもを待つことが難しくなることも多々あると思います。
「待てないときもある」と自分の気持ちを認めながら、対処法を参考に子どもと無理なく向き合っていきましょう。
子どもをできれば待ってあげたいと願う保護者の方のヒントになれば嬉しいです。
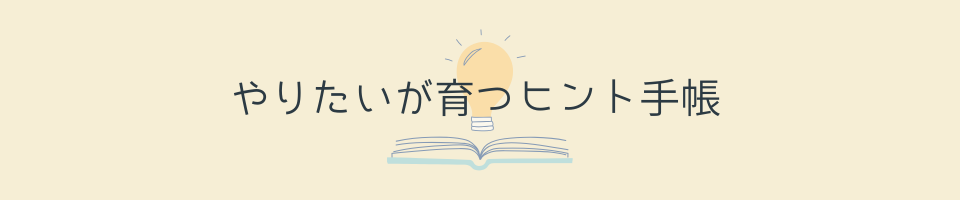



コメント