「子どもたちの主体性を育てる保育」と聞いて、どんなイメージを持ちますか?
自分で考え行動できる子どもを育てたいと思う一方で、「自由にさせるだけではダメなのでは?」「何をどこまで見守ればいいのか分からない」という悩みを抱える保育者や保護者の方も多いでしょう。
この記事では、主体性保育とは何か、大切と言われる背景、そして実践するための具体的な関わり方まで、詳しく解説していきます。
主体性保育って何?
主体性保育とは、子ども自らやりたいことを決めて、目標達成に向けて自分で考え、行動する力を育てていこうというものです。
単なる「自由保育」とは異なり、大人が一方的に指示を出すのでもなく、かといって完全に放任するのでもありません。
子どもたちが「自分でやってみたい!」という内発的な意欲を大切にし、その過程を支えることが主体性保育の基本です。
困ったときにはサポートしますが、子ども自身の試行錯誤や気づきを奪わないように見守ります。
主体性保育が大切と言われる理由
では、なぜ、主体性保育が大切だと言われるようになったのでしょうか。
日本では、これまで「言われたことができる子」が良しとされる文化が根強くありました。テストの点数や成績表など、数値で評価できる「認知能力」の方が重視されていたのです。
しかし、社会の変化とともに、正解のない課題に向き合う力や、自分で考えて行動する力が求められるようになり、「非認知能力」にも注目が集まるようになりました。
特に、2018年の保育所保育指針の改訂では、「子どもが自己を十分に発揮しながら主体的に活動できる環境の構成」が強調され、保育現場でも主体性を育む取り組みが重視されるようになりました。
主体性と自主性の違い
主体性とよく間違われるのが、自主性です。この2つは似ているようで、明確な違いがあります。
・主体性・・・「自分はどうしたいか」という意思に基づき、自ら考えて行動すること。
・自主性・・・与えられた課題や枠組みの中で、自ら考えて行動すること。
たとえば、ひな祭りの製作で子どもが「おひなさま作りたいな」と思って、どんなおひなさまにするかや、使う材料を自分で決めて取り組んでいくのが主体性です。
一方で、保育士から「このおひなさまを作るよ」と決められた中で、どんな色を使うか考えて作るのは自主性にあたります。
主体性を育むためには、子ども自身が「何をしたいか」考えられる機会を意図的に作ることがポイントです。
子どもの主体性を育むための関わり方
ここまでは、なぜ主体性保育が大事だと言われているのかを見てきました。
それでは実際に、子どもの主体性を育むための関わり方のポイントを3つ紹介します。
ぜひ参考にしてください!
子どもの姿を見守る
主体性保育を行う上で、保育者は「先回りして手助け」するのではなく、「困ったときにそっと支える」スタンスが大切です。
子どもが悩んでいるとき、ついアドバイスをしたくなりますが、すぐに答えを与えるのではなく
「どうしたらいいかな?」
「ほかに方法がないかな?」
と問いかけながら、子ども自身が考える時間を作るようにします。
失敗したり、遠回りしたりすることもありますが、答えをすぐに与えられないことで、子ども達は自分で乗り越える経験を積んでいきます。
子どもの姿を見守る姿勢を持ち、主体性を育んでいきましょう。
子どものやりたいを引き出す環境づくり
主体性保育では、子どもの「やりたい」を引き出せる環境を作ることが大切です。
たとえば、様々な素材や道具が使えるコーナーを用意したり、天気や季節に合わせて自然体験を取り入れたりします。
子どもがどんな遊びに興味があるかを見極めて、おもちゃを用意するのもよいでしょう。
環境そのものが子どもに語りかけ、「これを使ってみたい」「やってみようかな?」という気持ちを引き出せるような設定を意識してください。
子どもの「やりたい」気持ちを刺激する環境は、主体性をグングン伸ばしていきますよ。
子どもの小さな意思表示を見逃さない
主体性は、大きな決断だけではなく、日々の小さな選択から育ちます。
「今日はお外で遊びたい」
「まだ遊んでいたい」
というような子どもの小さな意思表示を丁寧に拾い上げましょう。
子どもの意思を尊重することで「自分は大切にされている」という安心感と、「自分で選んでいいんだ」という自信が育ちます。
状況によっては、子どもの意思すべてを汲み取ってあげるのが難しいこともあるかもしれません。
そのときは、「そうだね、〇〇したいよね。」と気持ちを受け止めるだけでも、子どもは「自分の思いを受け止めてくれた」と安心できますよ。
子どもの主体性を育てるために、小さな意思表示を受け止めてきましょう。
【はじめての主体性保育】Q&A
関わり方を知ると、「どうしたらいいのかな?」と感じる場面も出てくるでしょう。
ここでは、主体性保育をしているとよく出てくる疑問についてお答えしていきます!
どこまで見守ればいいの?

子どものやりたいってどこまで見守ればいいの?

子どものやりたいは、できる限り尊重する。でも決められた時間はあるから、約束事も伝えながら今後は子どもが自分でどうするか決めていけるようにする!
基本的には、子どもの意思を尊重しましょう。
子どもは自分の意思を受け止められたことで、「大切にされている」という安心感や「選んでいいんだ」という自信を得ます。
しかし、どうしても聞いてあげるのが難しいときには、約束事を伝えて子どもに「どうするか」考えてもらいましょう。
たとえば、給食の時間だけど食べたくないと子どもが言ったとき。12時までには食べて下膳をしなければいけないと決まっていたとします。
そんなときは、「そうだよね、遊びたいよね。給食の時間が決まっていて、12時までには食べてほしいんだ。給食を食べたあとに遊ぶか、あと少しだけ遊んで食べるか、どうする?」と聞いてください。
気持ちを受け止めて提案をすることで、子どもの意思を尊重しつつも自己決定の場を作れます。
「あなたの思いを尊重したい」という姿勢を見せることが大切です。
子どもがわがままにならない?

子どものしたいことばかりを聞いていたらわがままになりそう・・・
子どものやりたいことばかりを尊重していたら、わがままになるのではないかという不安はよくある心配事だと思います。
主体性保育は、子どものやりたい気持ちは尊重しますが、何でもやってOK!ではありません。
命の危険に関わることは止めなければいけませんし、ルールも伝えていきます。
その中で子どもは自分でどうするか考えて行動するようになっていくため、わがままにはなりません。
むしろ、主体性が育っている子は自分のことに責任を持つようにもなるとも言われていますね。
また、自己肯定感の高い子どもは、他者も大切にできるため、相手が困るようなことはしないでしょう。
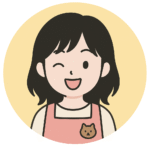
主体性保育で子どもはわがままになりません!自分のしたいことを主張することはわがままではないと理解しておきましょう。
まとめ:主体性保育で子どもの生きる力を育もう!
主体性保育は、子どもたち一人ひとりが自らの興味関心に基づいて生き生きと成長していくための大切な土台を作る保育です。
保育者にとっては、従来の「教える」「指導する」という役割から、「寄り添い」「引き出す」という役割への意識の転換が求められます。
「この子は何に心を動かされているのか」「今、どんな選択をしようとしているのか」――日々の小さなサインを大切に受け止めながら、子どもの主体性を育んでいきましょう。
未来を生きる子どもたちにとって、主体性はかけがえのない力になります。
一人ひとりの輝きを信じ、支える保育をともに目指していきたいですね。
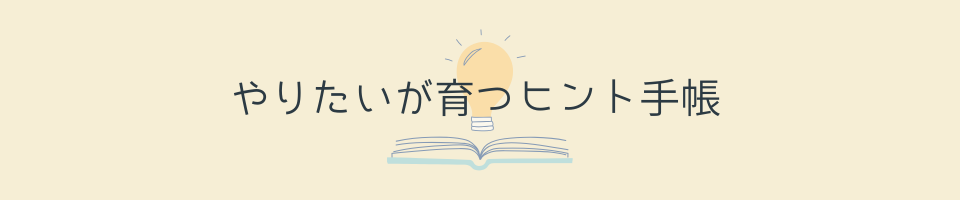
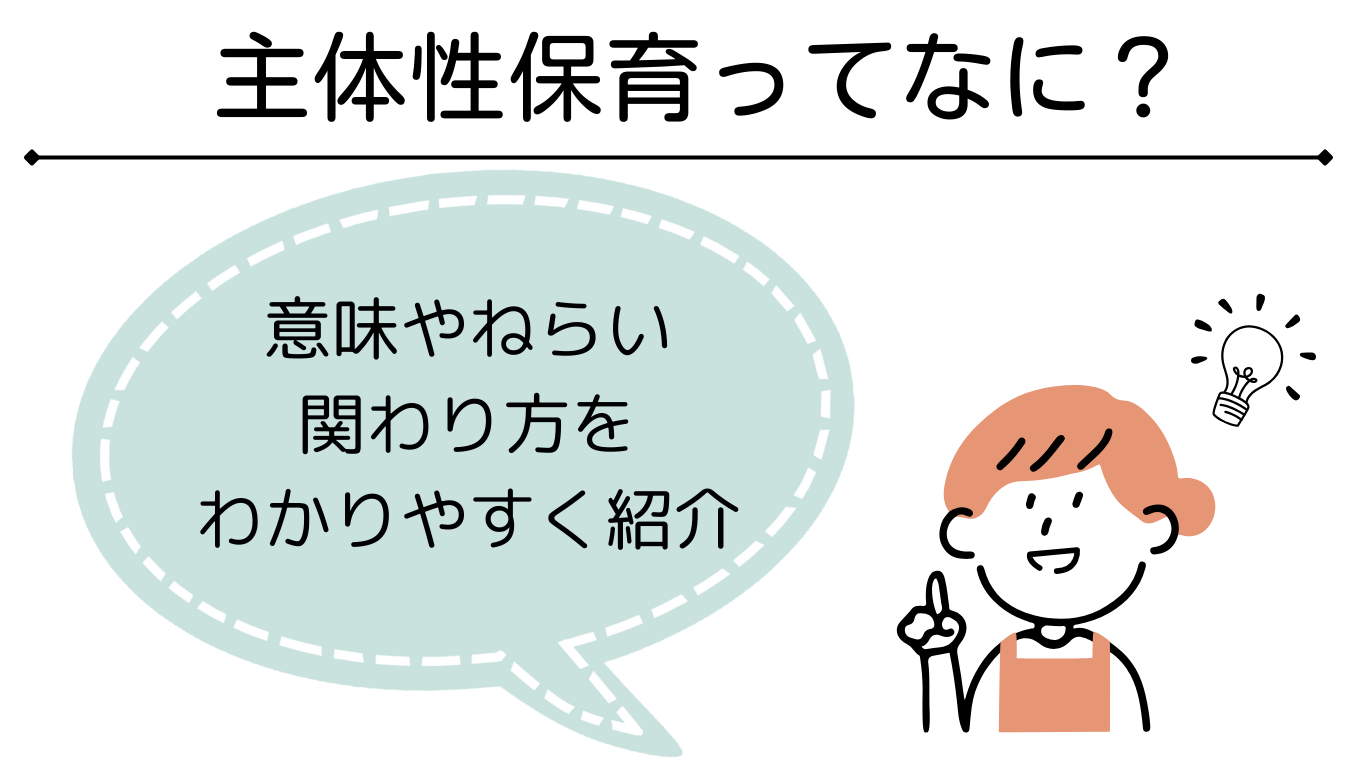
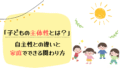
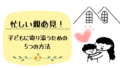
コメント