お昼の時間になり子どもを誘うと、「ごはん食べない!」と言われてしまった経験はありませんか?
実はこれ、保育園の2歳児クラスではよくある風景です。
イヤイヤ期の最中でもあり、なんでも「イヤ!」と言いたくなるお年頃なのです。
でも、親からしたらせっかく作ったお昼を食べてもらえないのは悲しいですし、保育士さんであれば、お腹がすいてしまうから食べてほしいと思うのではないでしょうか。
今回は、私が経験した「ごはんを食べない!」と言った2歳児に対して、
✅どのような対応をしたか
✅見守ると関わるの線引きはどこか
✅保育士が実践する対応法
を書いています。

我が子がごはんを食べないというけど、どうしたらいいの?

保育園で食べないという子にはどう対応したらいい?
と悩む方のヒントになれば嬉しいです。
私が経験した2歳児の「ごはん食べない!」
私が経験したエピソードを紹介します。
給食の時間が始まったときのことです。
保育士に誘われて、1人、また1人と自分の席についていく中、なかなか行かずにウロウロしている子がいました。
私はその子に「ごはん用意できたよ。食べに行く?」と誘いました。
すると、「やだ!」「ごはん食べないの。」という声が返ってきました。
私の対応と考えたこと
誘いを断った子は給食だけではなく、何に対してもはじめは「やだ!」から始まる、イヤイヤ期のお手本のような様子でした。
しかし、食べることは好きで、よくおかわりをしています。
今日の給食が何か分かったら食べたくなるかもしれないと考えて、「ごはん見に行ってみる?」と声を掛けました。
もちろん返ってきた答えは「やだ!」。

あ!今日ゼリーだよ!なに味かな?確かめてみる?

やだ!

○○ちゃんも食べてるね。おいしそうだなぁ

やだ!
いろいろと声を掛けてみましたが、ダメ。
イヤイヤ期真っ只中のお子さんを育児中の方や、1歳、2歳児クラスを持っている先生からしたら、よくある場面ではないでしょうか。
私は、「そっか~。食べたくないんだね。」と気持ちに共感し、そっとその場を離れました。
少し時間を開けてからまた誘ってみようと思ったのです。
もしかしたら、他の子が食べているのを見て、食べたくなるかもしれません。
子どもが自分で食べるという選択ができるように、『待つ』ことにしました。
ほかの先生の対応
私が離れて食事の準備をしている間に、ほかの作業をしていた保育者が「ごはん食べないの?」と声を掛けていました。
答えは「やだ!食べない」でしたが、その保育者はその後も声を掛け続け・・・。
最後には抱っこで給食を見せて、食べる意欲を引き出すことに成功していました。
「見守る」か「関わる」かは、子どもを見て考えることが大切
私はこのことから、「見守る」と「関わる」のバランスは、どちらが正しいかという問題ではなく、子どものその時の気持ちや状況をどう受け取るかが大切だと感じました。
今回のように、関わったことで給食を食べられることもあれば、待つことで食べたくなり動き出す子もいます。
大切なのは、「今この子にとって必要なのはどちらか?」を考える視点を持つこと。
その判断には、子どもの性格や関係性、その日の気分など、さまざまな要素が関わってきます。
また、保育者によって対応に違いがあると、子どもが混乱したり、大人同士のすれ違いにもつながります。
そのため、保育者同士で「見守るか、関わるか」の視点を共有しておくことが大切だと、あらためて感じた出来事でした。
保育士が実践するごはんを食べない子の対応法
ここまでは、私の実際に経験したエピソードを紹介しました。
では実際に、ごはんを「食べたくない!」と拒否する2歳児に対して、どのような関わり方があるのでしょうか。
ここからは、私が日々の保育の中で実践している具体的な対応法をご紹介します。
ポイントは、子どもの「今」に合わせて、大人のかかわり方を選ぶという視点です。
対応に困っている方の参考になると嬉しいです。
少し待ってみる
私がおすすめするのは、待ってみることです。イヤイヤ期では子ども自身が選ぶと、スムーズにいく場合があります。
個を確立しようとしている子どもにとって、自分の意思で「食べたい」と決定したことが重要であるからです。
イヤイヤ期にいる子どもを保育している人たちは、「すべての手を尽くしたけど、嫌だと言われてしまうためどうしたらよいか?」と悩むことが多いと思われます。
一生懸命誘っても来ないのであれば、一度引いてみましょう。一緒にご飯を食べようと考えていたのであれば、先に食べてしまっていてもいいと私は思います。
食べている様子を見たら食べたくなる可能性もあります。
今回の件とは別で、2歳児がごはんを食べないと言っていたときがありました。しかし、ほかの子が食べている様子を見ていると、誘わずとも自分で手洗いをして席につくことがありましたよ。
その際ごはんに誘う声掛けなどはしていないので、待ってみると意外と子どもの方から動いてくれるかもしれません。
働きかけても子どもに断られる場合は、待ってみてください。
対応する人を変える
いくら声を掛けても「イヤ!」と言われるときは、対応する人を変えるのも1つの手です。
先ほどのエピソードにも書いた通り、対応する人が変われば子どもの気持ちも変わることがあります。
大切なのは、職員同士やお父さん、お母さんの中で関わりの流れを把握しておくこと、どこまで見守り、関わるのかをすり合わせることです。
今までしていた関わりを知らずに再度何度も声を掛けてしまうと、「さっきから嫌だって言っているのに!」という気持ちになってしまいかねません。
人によって対応が変わると、守るべきルールがわからず子どもも混乱します。
対応する人を変えるときは、どのように関わったかを引き継いでから託しましょう。
また、日頃からどこまで見守るのかを話し合うと、対応に差が出ずに済みます。
嫌がる子どもには1人で対応しようとせず、みんなで関わっていく意識を持つと心に余裕が出ますよ。
ぜひ、実践してみてください。
無理して食べさせなくていいという気持ちを持つ
無理して食べさせなくていいという気持ちを持つと、自然と心に余裕が出て、イヤイヤ期の対応も苦ではなくなります。
せっかく用意したごはんや給食を「イヤ!」と言われると、嫌な気持ちになるもの。
私たち大人は、その食事にどれだけの労力がかかっているかが想像できるからです。自分で作ったものであれば、なおさらですよね。
しかし、子どもにはまだそこまで想像する力はありません。
いくら「もったいないよ!」「せっかく作ってくれたんだから!」と言われても、よくわからないのです。
そのため、「嫌なら食べなくてもいいか」という気持ちを持つと同時に、子どもに自分の選択を振り返る機会にしましょう。
たとえば、最後の声掛けの時に、「ここまではごはんが食べられる時間だけど、それを過ぎたらごはんを食べられなくなってしまうよ。いいね?」と子どもに伝えます。
2歳であれば、わからない子が多いでしょう。
「次先生が声を掛けたときに食べないと、ごはんの時間が終わっちゃうよ。」
「次に食べられるのは、寝て起きた後のおやつだよ。」
だと比較的に伝わりやすいかもしれません。
子どもは食べられない経験をすると、「あのときに行かないと、食べたいときに食べられないんだ」と学びます。
この経験こそが、子どもが自分の選択したことへの責任を持つということなのです。
モンテッソーリ教育の中でも、子どもが自分で選び、その結果を経験する機会を大切にしています。
たとえば、教育者の大原青子先生は、インタビューの中で「子どもが自分で選び、その選択した結果を体験することで、ルールを守れるようになる」と語っています。
選択した結果を受け「こうしたほうがいいんだな」と感じることができると、ルールを守った方が得だとわかり、自分から約束事を守るようになっていきます。
こうした視点からも、「無理に食べさせる」のではなく、「食べる、食べない」を子ども自身が選び、その結果(お腹が空いた、次のごはんまで待たないといけない)を経験させることは、貴重な学びの一つだといえます。
もっと詳しく知りたい方は、大原先生のインタビュー記事がとても参考になります。
👉【大原青子先生インタビュー③ 自由の意味とルールの伝え方】 idees montessori
各保育園の方針にも寄りますが、出さないと問題になる場合もありますから、園長先生に確認したうえで対応を考えてください。
「食べたくないならいいか」という気持ちを持つだけで、イヤイヤ期の対応も楽になります。
また、子どもに自分の行動に責任を持つことを学んでもらう機会にもなるので、無理に食べさせようとはせず、気楽に向き合ってみることをおすすめします。
まとめ:子どもの様子に合わせて、イヤイヤ期も気楽に向き合おう
いかかでしたか?
今回は、私が経験した『ごはんを食べたがらない2歳児』のエピソードを紹介しつつ、ごはんの場面に限り、イヤイヤ期にいる子どもへの対応を書きました。
なにげない「イヤ!」でも、大人からするとだんだんと嫌な気持ちになったり、イライラしてくるもの。
「食べたくないならいいか」「食べたくなったら食べる」という考えを心に持っておくと、余裕が出るためおすすめです。
保育の現場であれば、子どもをどこまで見守り、関わるのかを職員同士でのすり合わせが大切です。
子どもの発達によっても変わるでしょうから、1人ひとりの育ちやそのときの気持ちを把握したうえで、対応を考えてください。
ごはんの場面で嫌がる子への対応に悩む方の参考になれば嬉しいです。
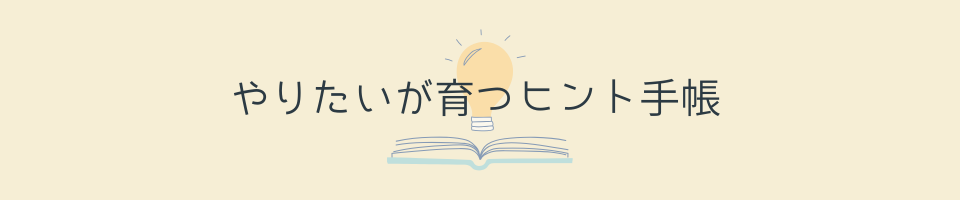
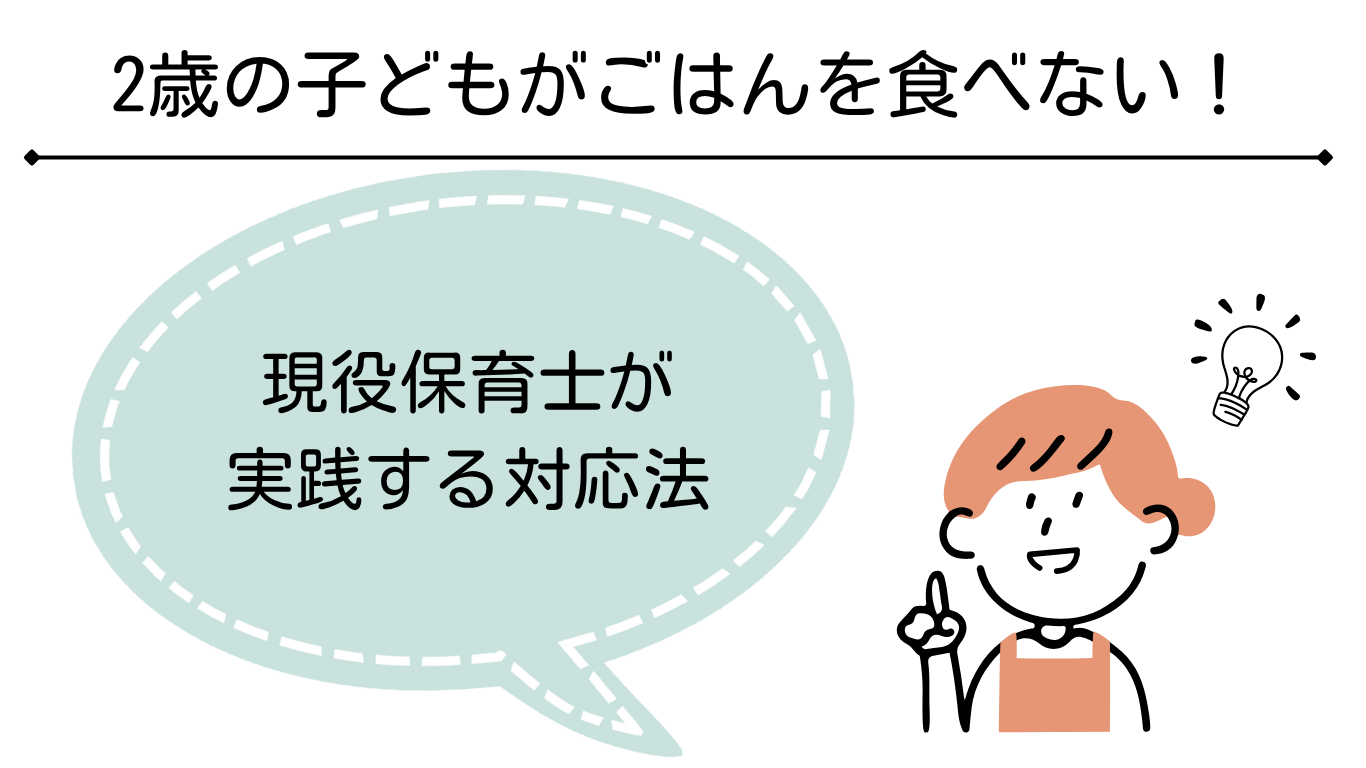

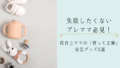
コメント