
こんにちは!あさのです!
9月になりましたね。
まだまだ暑い日が続きますが、道にはあるものが落ちているのを見かけるようになってきました。
それは・・・どんぐり。
どんぐりを見ると自然物で遊ぶのが楽しい季節になったなと感じます。
でも、自然物は拾ったら製作に使って終わりになりがちではありませんか?
そこで今回は、自然遊びをテーマに
✅主体性を育むためにはどのように見守っていけばいいのか?
✅自然遊びの展開の仕方は?
主体性を育む視点からご紹介します。
これから自然遊びを増やしていこうと考えている保育士の方の参考になれば幸いです。
自然遊びが主体性を育む理由
自然遊びでは、子どもの主体性を育めます。
というのも、以下の3つが理由です。
- 遊び方がたくさんある
- 素材が豊富
- 発見が多い
ひとつひとつ見ていきましょう。
遊び方がたくさんある
自然遊びには正解がありません。
大人が用意したおもちゃのように、「こうすべき」という決まりがなく、子ども自身で遊び方を見つけられる点が子どもの主体性を育むことにつながります。
素材が豊富
秋の自然物に限りませんが、どんぐりやまつぼっくり、落ち葉などたくさんの素材があります。
様々な感触、色、形があることで子ども達が「どう遊ぼうかな?」と考えやすくなります。
発見が多い
自然遊びでは、虫を見つけたり葉っぱの色の違いに気づいたりと、発見が多くあります。
これらは保育士からの促しではなく、遊んでいるうちに子ども自身が見つける機会が多々あるため「主体的な気づき」を得られるのです。
自然は毎回違うので、子ども達の好奇心も途切れません。
主体性保育の視点で考える自然遊びの進め方
では実際に自然遊びをしようとしたときに、どのように進めればいいのでしょうか。
- 素材集め
- 遊び方の観察・試す
- 遊びの発展
この3ステップを頭に入れておくと、子どもの主体性を尊重しながら自然遊びが進められます。
子どもの発見は無限大です。私たちが予想もしなかった遊びをすることもあるでしょう。
そんな子どもの姿も楽しみながら、自然遊びをしてみてくださいね。
1.素材集め
まずは、遊べる素材を集めます。
このときも、子どもの主体性の芽を育むポイントがあります。
それは、「たくさん集めよう!」や「これがいいんじゃない?」ではなく、「どれがいいかな?」と問いかけながら行いましょう。
自分(子ども)は「どれがいいか」「何が気になるか」考えることで、その子ならではの視点が生まれます。
たくさん集めるもよし、お気に入りだけ集めるのもよし、です。
大人の価値観で「こうした方がいいよ」と言って進めないようにすると、子どもの個性も感じられますよ。
2.遊び方の観察・試す
遊べるものを集めたら、次は子どもがどう遊ぶか観察しましょう。
転がす、破く、音を出すなど様々な遊び方が見られると思います。
どうやって遊べばいいか悩む子がいるのであれば、保育者がちょっとだけやって見せてください。
子どもが興味を持ち、真似し始めたらあとは見守ります。
ポイントは遊び方を決めつけずに、きっかけだけを示すことです。
3.遊びの発展
子ども達が遊び始めたら、自分で「こうしよう」と決めた姿を見守りながら、環境を整えていきます。
たとえば、
・どんぐりを段差から転がしている→コース作りができるよう段ボールなどを用意する
・まつぼっくりを水で濡らしている→たらいを用意して水に浮かべられるようにする
・落ち葉をやぶって容器に集めている→ごっこ遊びや色分け遊びができるようおもちゃを揃える
注意点は、「こうしてみたら?」と声を掛けないこと。
保育者の思い描く遊びに誘導してしまうと、子ども自身の視点が失われてしまいます。
困っていたら提案はするけれど、あくまでも環境を整えて子どもの遊びが深まるお手伝いをする、と心掛けましょう。
子どもの主体性を育む保育士の関わり方のポイント
自然遊びの進め方を紹介したあとは、どのように関わるかポイントをお伝えしていきます。
- 保育士が用意するきっかけは最小限にして見守る
- 試す過程を認める
- 遊びが広がる瞬間を見逃さない
子どもの主体性を伸ばしていくためには、保育士の関わり方も大切です。
ポイントを簡単に紹介するので、参考にしてください。
保育士が用意するきっかけは最小限にして見守る
保育士が用意するきっかけは最小限にして、見守ることに徹しましょう。
たとえば、保育士がどんぐりを手に取り振ってみせるとします。
それを見た子どもが「音がするね!」と気づき真似してみる。
そのあとは、子どもがどう遊ぶかを見守ります。
つまり、「やってごらん」ではなく、保育士が自然と楽しんでいる姿を見せることがポイントです。
もし、反応がなければそのまま流してOKです。
遊びが始まるきっかけを少しだけ置いてあげることで、子どもが「やってみたい!」と思える余地が作れます。
興味を持って自分から何かをしてみようとすることが、主体性を育む第一歩です。
ぜひきっかけ作りと見守る姿勢を意識してみてください。
試す過程を認める
子どもは大人のようにすぐに形や作品を作るわけではありません。
ただ転がしてみたり、並べただけでも大切な『試しの過程』です。
子どもの遊ぶ姿を見て、「転がしてみたんだね」「葉っぱをいっぱい集めたんだね」と声を掛けてください。
こうした声掛けが子どもの「やってみてよかった」という気持ちを支え、さらに挑戦してみようという意欲につながります。
遊びが広がる瞬間を見逃さない
私が保育士の関わりの中で一番大切だと思っているのが、遊びが広がる瞬間を見逃さないことです。
たとえば、どんぐりを触っているだけの子が転がし始めたら、遊びが広がる瞬間といえます。
保育者はコースづくりができるような素材を置く、転がしやすいスペースを確保するなど、環境を整えましょう。
このような関わりをすることで、「こうしてみようかな?」という子どもの発想につなげられます。
まとめ
秋は自然遊びが活発になる季節です。
自然遊びは、子どもにとって発見が多い遊びであり、主体性を育むにはぴったりです。
子どもの「やってみようかな」「どうなるんだろう?」という興味関心を見逃さないようにし、遊びが広がるきっかけを置いて、主体性を育むお手伝いをしてみてください。
素材に触れて、試して、発展する流れを見守ることで、子どもの主体性がぐんと伸びますよ!
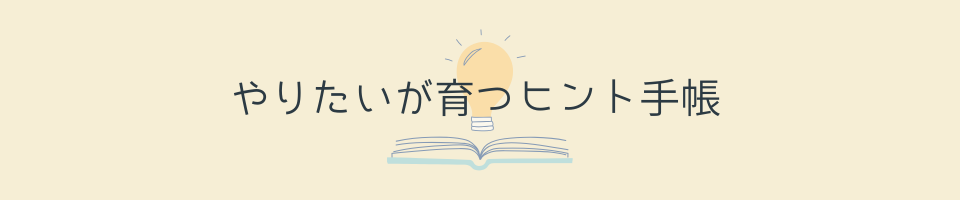
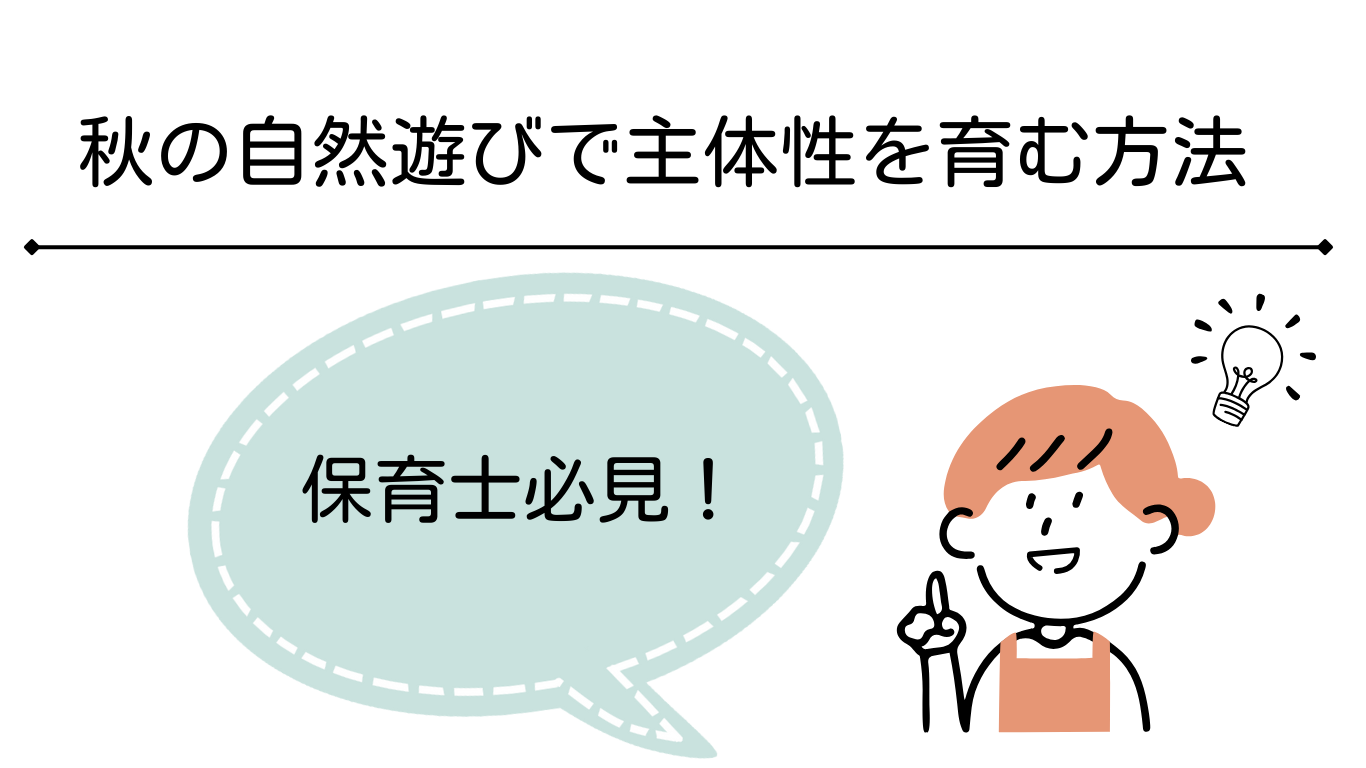
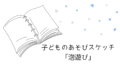
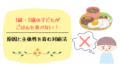
コメント