
こんにちは!保育士ママのあさのです!
毎日の育児、お疲れ様です。
先日、夫が2歳の子どもに顔を蹴られたときに発した言葉。
「ごめんね、は?」
たしかに顔を蹴られたら痛いし、相手に嫌なことをしたら謝るのは当たり前のことです。
ただ、2歳の子どもに「ごめんね」と言わせて意味があるのでしょうか?
私はただ言わせているだけの場面を見て少しモヤっとしました。
しかし、親としては悪いことをしたら謝れるようになってほしいと思うものです。
今回は、2歳の子どもが謝らない理由と、子どもが自然と謝れるようになる関わり方を紹介します。
「我が子はなぜ謝れないのか?」
「悪いことをしたら謝れるようになってほしい」
と願う保護者の皆様に届くと嬉しいです。
✅この記事でわかること
- 2歳の子どもが謝らない理由
- 「ごめんね」を促すとどうなるか
- 保育士ママが大切にしている関わり方
- 謝れるようになるのはいつ頃からか
2歳の子どもが謝らないのはなぜ?

2歳の子どもが謝れない理由は3つあります。
- 気持ちの理解がまだ難しい
- 悪いことをしたという認識が育っていない
- 「謝る」=「仲直り」という社会的ルールを学ぶ途中
なぜ謝れないのかを知っていると、子どもに「ごめんね」と言わせなければと思う気持ちが軽減できます。
気持ちの理解がまだ難しい
2歳の子どもは、まだ相手の気持ちの理解が難しいことが挙げられます。
たとえば、我が家の場合ですが・・・
仕上げ磨きの場面で、
- 嫌がる子どもが夫の顔を蹴った
- はじめは夫も軽く注意していた
- 目に当たったため真剣に注意し、「ごめんねは?」と促した
という流れでした。
我が子になってみると、こうです。

はじめは笑っていたのに、途中から怒られた。なぜ怒っているんだろう?
起こった出来事はわかっても、相手がどう感じたのかまでは理解できません。
悪いことをしたという認識が育っていない
我が家の例でいくと、2歳では「顔を蹴る」=「悪い」という認識がまだありません。
同じ年の子と遊んでいると、よくおもちゃの取り合いになるのではないでしょうか。
あれも実は、おもちゃを取ることがよくないことだとわかっていないために起こる出来事でもあります。
2歳はまだまだ自分中心の世界です。
ほしい!と思ったらおもちゃは取りますし、楽しい!と思ったら顔も蹴ってしまうこともあります。
いけないことを知らせていくためには、親が「見て、悲しそうな顔をしているね。」と相手の気持ちを代弁していくことがポイントになります。
「謝る」=「仲直り」という社会的ルールを学ぶ途中
自分中心の世界である2歳は、社会的ルールを学ぶ途中にいます。
謝ることで仲直りができることもまだ知りません。
ルールの学びは、人と人との関わりの中で育まれていくものですから、謝ると仲直りができると親が伝えていくことが大切です。
「ごめんねは?」と促されるとどうなるのか

いけないことをしたら謝れるようになってほしいと願う方は多いと思います。
しかし、親が「ごめんねは?」と促すと、年齢によっては「謝る」意味を間違って覚えてしまう可能性もあります。
子どもに謝ることを促し続けたとき、どうなってしまうのか見ていきましょう。
相手の反応を見て謝るようになる
「ごめんねは?」と促されて謝ることを身に着けた子は、相手の反応を見て謝るようになります。
相手が泣いているから、怒っているから謝っているだけで、「なぜいけなかったのか?」「相手はどういう気持ちになったのか」を理解しないまま謝るようになってしまいます。
そういう子が将来どうなるかは想像できますよね。

なんでごめんって言ってるかわかってるの?!
こうならないためにも、相手がどう感じたのかを伝えていく必要があります。
「ごめんね」を言わない=悪い子と感じてしまう
「ごめんねを言わないといけない子なんだ」と感じてしまう恐れがあります。
先ほどの内容とも少し重なりますが、人の表情を伺うようになってしまい、自己肯定感が低くなる可能性も。
そのため、解決のための「ごめんね」ではなく、なぜ謝るのかを伝えていくことが大切です。
詳しい関わり方は次の項目で紹介します!
保育士ママが大切にしている3つの関わり方

謝れる子に育ってほしい場合、どのように関わればよいのでしょうか。
ここからは私が大切にしている3つの関わり方をご紹介します。
気持ちを代弁する
まずは、子どもの気持ちを代弁しましょう。
叱らずに気持ちを代弁してあげることで、子どもは自分自身がいけないわけではなく、行為がいけなかったと安心します。
我が家の例でいくならば、「パパと遊ぶのが楽しかったんだね。」と声を掛けます。
おもちゃを取ってしまったならば、「おもちゃが使いたかったんだね。」と伝えてあげてください。
「どうしたかったの?」と声を掛けるのも効果的です。
はじめに、気持ちを受け止められると子どもは安心感を持って話を聞くことができます。
相手の気持ちを知らせる
気持ちに寄り添ったあとは、相手の気持ちを知らせます。
自分の行為が相手にとってはどうだったのかを知る機会を作ることで、相手がどう感じたかを想像できるようになり、やがて「謝ろう」という気持ちに繋がります。
声掛けの仕方としては、
「見て、悲しそうな顔をしているね。おもちゃ使ってたのかな?」
「泣いているね、痛かったのかもしれないよ。」
ポイントは、相手の感情を見える形で伝えてあげることです。
まだ他の人の感情を察することは難しいので、わかりやすく視覚と言葉で伝えてあげましょう。
謝ることよりも気持ちを通わせることを大切にする
その場では謝れなくても大丈夫です。謝ることよりも、気持ちを通わせることを大切にします。
「ごめんね」と言わせることが目的になってしまうと、本当の意味で謝れなくなってしまいます。
2歳はまだ自分から謝るのが難しい年齢です。
「友達が悲しそうだね。悲しい気持ちにさせてしまったときは、ごめんねって言うんだよ。」
と解決方法を伝えたら終わりにしましょう。
そこで謝れるかもしれないし、謝れないかもしれない。
でも、謝れないから悪いではありません。
自分はどういう気持ちだったのか、相手はどう感じたのかを学ぶ方が大切です。
その学びや経験から、自然と謝れるようになっていくのです。
ごめんねと言えるようになるのはいつ頃から?
4歳ごろから相手の気持ちに気づけるようになってくる
4歳ごろになると、相手の気持ちに気づくようになってきます。そのため、自分が何かして相手が悲しんでいると「ごめんね」と言うこともあります。
ただし、「自分が間違っていると認めたくない」「謝る=負け」と思う時期でもありますので、素直に謝るのは難しい場合もあります。
心から「悪い」と思って「ごめんね」と言えるのは、5歳以降と考えてもよいでしょう。
謝るという行為は、様々な育ちが揃ってからできることで、子どもにとっては意外とハードルが高いことがわかったのではないでしょうか。
まとめ:「ごめんね」を言わせるより、気持ちに寄り添い通い合わせることを大切に
2歳の子どもはまだ発達的にも自分から「ごめんね」と言うことが難しい場合があります。
自分中心の世界であったり、相手がどう思ったかまでを察せないことが謝れない理由の1つです。
将来、悪いことをしたら謝れる子になってほしいと願う場合は、今から3つのポイントを大切にして関わってみてください。
- 気持ちを代弁する
- 相手の気持ちを知らせる
- 謝ることよりも気持ちを通わせることを大切にする
今大事なのは、謝れることよりも気持ちを通い合わせることです。
焦らず長い目で子どもの成長を見守っていきましょう。
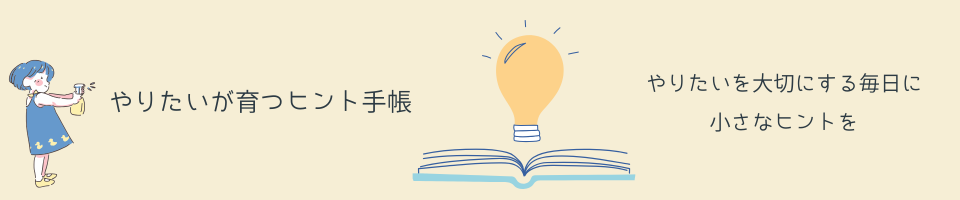

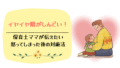

コメント