「非認知能力が大切」と耳にすることが増えてきて、我が子にもあった方がいいのかな?と気になっているのではないでしょうか。
非認知能力とは数値では測れない能力のことを指し、日常や社会活動において大切な影響を及ぼすと言われています。
本記事では、非認知能力とは何か、そしてなぜ大切だと言われているのか、さらに育った子の特徴を説明します。
あわせて、家庭でもできる非認知能力を育む関わり方をご紹介!
非認知能力に興味がある方の参考になれば嬉しいです!
非認知能力とは?
非認知能力とは、数値で測ることができない力を指します。例えば課題に向き合う力や、自分で考えて行動する力などは非認知能力のうちの1つです。
反対にテストの点数や成績表など、数値で評価できるものは認知能力と言います。
「非認知能力」・・・数値では測れない内面的な能力
「認知能力」・・・点数や成績表などで数値化できる能力
非認知能力は近年、教育現場において注目されています。
ではなぜ非認知能力が注目されていて、大切であるかを説明していきます。
非認知能力が大切な理由
非認知能力が注目された理由は、ある研究結果にあります。
1960年に行われた「ペリー就学前プロジェクト」で、幼児教育を受けたグループは、高卒率や就業率が高く、犯罪率が低いなど、社会的に良い結果が得られたことが示されました。
この研究では、子どもたちの意欲や社会性などの力(=非認知能力)を育むことが重視されていました。そこから、学力だけでなく、非認知能力も人生において重要だと考えられるようになったのです。
現在は、情報化社会で自分で何が正しいのかを見極め、選択していく力が求められます。
多様化が進む時代を生き抜くために、再度、非認知能力が注目されているのです。
非認知能力が育っている子の特徴
非認知能力が育っている子の特徴は、いくつかあります。
・目標を達成する力がある
・周りの人と協力できる
・自分の気持ちをコントロールする力に長けている
我が子に非認知能力があるかどうか気になる方は、参考にしてください。
目標を達成する力がある
非認知能力が育っている子は、目標を達成する力があります。
目標を達成できる子は、意欲や忍耐力、自尊心などがある証拠です。
目標を達成するためには、意欲が高くないと続きません。また、困難に出会ったときに耐える力もないと成し遂げられません。
「自分にはできるぞ」という自尊心もモチベーションを保つうえでは重要でしょう。
そのため、目標を達成する力がある子は非認知能力が育っていると言えます。
周りの人と協力できる
周りの人と協力できることも、非認知能力が育っている子の特徴です。
たとえば、相手の気持ちを考えて行動したり、役割を分担しながら一緒に作業できたりする姿は、協調性や思いやりの表れです。
こうした行動ができる子どもは、自己肯定感があり、相手を信頼する気持ちが育っています。
自分を大切にされる経験があると、他人の気持ちも自然と大切にできるようになり、人と協力して物事を進めることができるのです。
自分の気持ちをコントロールする力に長けている
自分の気持ちのコントロールが上手であれば、非認知能力が育っているサインかもしれません。感情を制御できる子は、自分自身に自信があったり、自尊心が高い傾向にあります。
たとえば、課題に対して達成が難しくても落ちこまずに「次も頑張ろう」「自分にはできる」と挑戦し続けられる子は、自分の気持ちをコントロールできている証拠です。
また、自尊心が高い子は「自分は自分でいい」という考えを持っているため、他人と比べて嫌な気持ちになることもありません。
ちょっとしたトラブルや思いどおりにいかない場面での子どもの様子に、非認知能力の育ちを感じ取れるかもしれませんね。
非認知能力を伸ばすための5つの関わり方
ここまでは非認知能力とは何か、育っている子の特徴について見てきました。ここからは、実際に非認知能力を伸ばすための関わり方を伝えていきます。
- 子どもに愛情を注ぐ
- 興味を持ったことは応援する
- 子ども自身が決める経験をさせる
- 失敗しても前向きな声掛けでサポートする
- 頑張った経過や行動を褒める
どれも家庭でできる簡単な関わりです。ぜひ試してみてください。
子どもに愛情を注ぐ
子どもに愛情を注ぐことは、なによりも大切な関わりです。「自分は愛されている」と感じられると、自己肯定感が高まります。
自己肯定感を高めるためには、子どもに「大好きだよ」と言葉で伝えたり、ハグをしたりしましょう。寝る前や朝起きたときなど、場面を決めて1日に1回は伝える習慣にすることがおすすめです。
子どもが「自分は大切にされている」「ありのままの自分でいいんだ」と感じることができると、自分自身だけではなく他人も大切にできます。また、困難なことに直面しても、立ち直る力を得られます。
子どもに言葉やスキンシップで愛情を伝えて自己肯定感を育み、非認知能力を伸ばしましょう。
興味を持ったことは応援する
子どもが興味を持ったことを応援すると、非認知能力を伸ばせます。気になったことに全力で取り組むと、集中力が育ちます。
興味を示したことは基本的には見守る姿勢を持ちましょう。年齢が大きくなれば、興味のあることを探しに出かけることもおすすめですよ。
0〜1歳児で例えるなら、ティッシュを引っ張る遊びが挙げられます。
一見大人にはいたずらに見える遊びも、子どもにとっては研究です。引っ張ったらどうなるのか、どうやって引っ張るのかを遊びの中から学んでいるのです。つい止めたくなりますが、できる範囲で見守りましょう。
好奇心は子どもの原動力です。大人がそれを理解してサポートすると、非認知能力を育むことに繋がりますよ。
子ども自身が決める経験をさせる
非認知能力を伸ばすためには、子ども自身が決める経験が大切です。小さな選択でも繰り返していくと、自分で選び取る力や自信が育ちます。
子どもに選んでもらう場は、家庭でも簡単に用意できます。
例えば、今日着る服やおやつで食べるものを選んでもらう。これだけでも子どもの決断力は磨けます。
乳児のうちは、選択肢が多いと選びづらいため、2つのうちどちらがいいかを選んでもらうことがおすすめです。
実際に我が家では、おやつに使うお皿も選ばせていますよ。
子どもが自分の意思で選ぶ経験を積んでいくことで、将来迷った時に自分で判断ができる力が身につきます。「自分で選ぶ・決める」場を積極的に作っていきましょう。
失敗してもポジティブな声掛けでサポートする
非認知能力を育てる関わり方の1つに、子どもが失敗したとき、ポジティブな声掛けでサポートすることが挙げられます。
前向きな言葉を掛けてもらうと、失敗してもまた挑戦しようとする意欲が育まれます。また、簡単に挫けない心も手に入れられます。
具体的には、「惜しかったね!次はどうしたらいいのかな?一緒に考えてみる?」と”次に繋がる”ように声を掛けることがポイントです。
そうすると、子どもは失敗したその先に意識を持っていくことができます。
このような経験を積んでいくと、失敗で多少落ち込むことはあっても「次はどうしたらいいか」を考えるクセがつきます。
「失敗しても大丈夫」「次どうすればいいかを考えればいい」と思えるようになると、トラブルに出会っても諦めない精神力も育めますよ。
子どもが失敗したときは、前向きになれる声掛けをして、忍耐力を身に着けられるようにしましょう。
頑張った過程や行動を褒める
非認知能力を育てるうえで大切なことは、結果だけでなく「過程」や「姿勢」に目を向けて声をかけることです。
うまくいったかどうかではなく、「最後までやりとげようとしていたね」「自分で考えてやってみたんだね」といった、頑張った行動に注目して褒めるようにします。
このような関わりを続けると、子どもは「挑戦すること自体に価値がある」と感じられるようになります。また、失敗を恐れず取り組んだり、粘り強く頑張ったりする力が自然と育っていきます。
子どもの努力やチャレンジした姿勢に目を向けることが、非認知能力を育てる大きな一歩です。
まとめ:非認知能力を伸ばして未来を生き抜く力を身につけよう!
非認知能力は、これからの時代を生きる子どもたちにとって欠かせない力です。
目には見えづらい力ですが、日々の関わり方や声かけによって、確実に育まれていきます。
非認知能力は、どれもすぐに身につくものではありません。
だからこそ、子どものペースを大切にしながら、日々の中で丁寧な寄り添いが必要です。
今回ご紹介した5つの関わり方は、家庭で簡単にできるものばかりです。
できることから始めて、子どもが持つ非認知能力の芽を育てていきましょう!
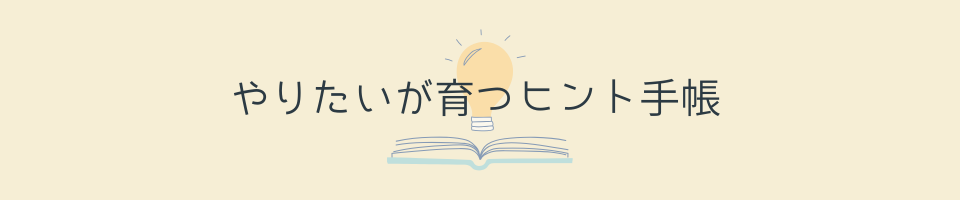
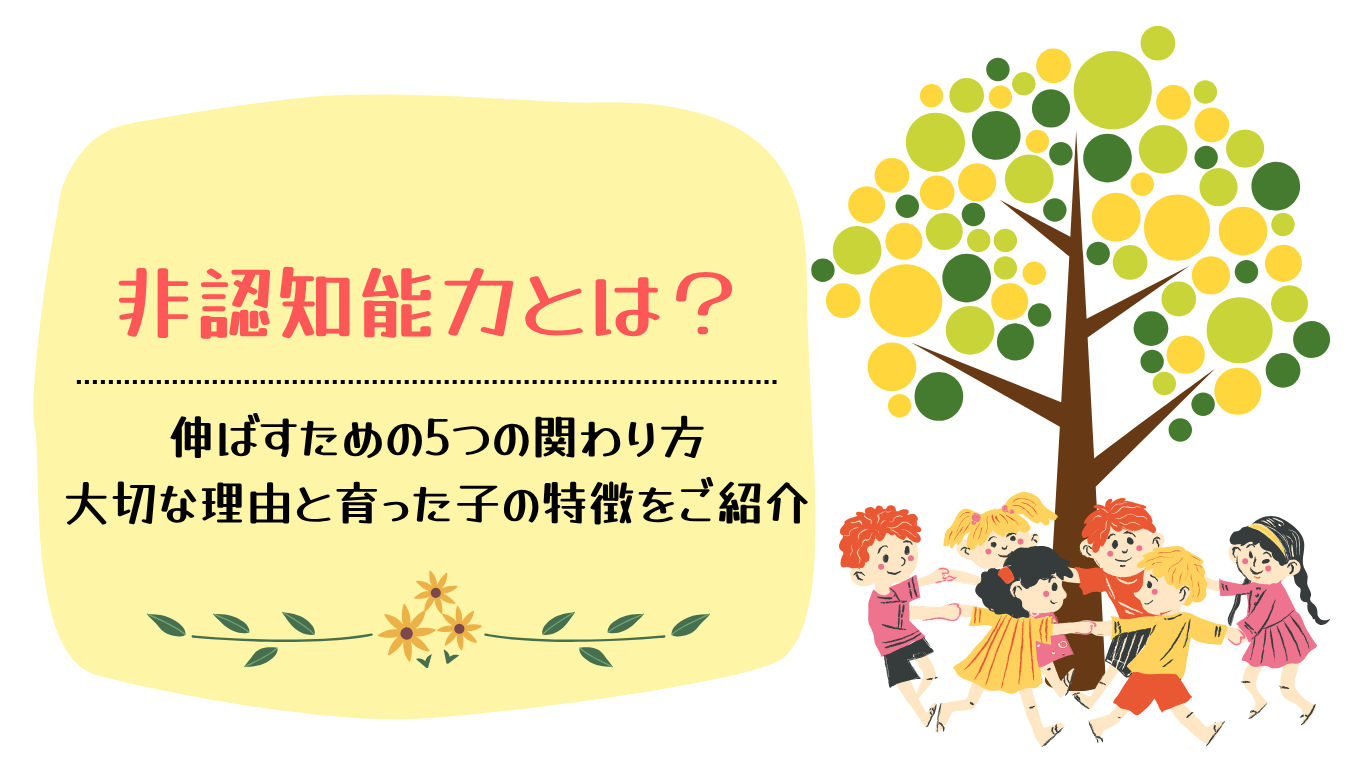


コメント