「まだ小さいからわからない」
育児や保育をしていてこう感じることはありませんか?
実は、主体性保育を知る前の私もそうでした。
しかし、ある出来事があってからは、子どもは大人が思うよりもわかっていると感じ、私の中で主体性の見え方が変わりました。
本記事では、実際にあったエピソードを交えて、子どもは自分で育つ力があるという話を紹介します。
主体性を育む関わり方も載せているので、日々の育児や保育のちょっとしたヒントになれば嬉しいです。
子どもは大人が思うよりもわかっている
私が子どもの主体性を大切にする園で初めて働いたときのことです。
それは片付けの場面でした。
”片付ける理由も伝えながらやって見せるとよい”
そう言われていた私は、「ほんとにそんなことで子どもは片付けるようになるんだろうか?」と思っていました。
半信半疑で、「踏むと危ないから、片付けようね〜」と言いながら片付けるのを繰り返していました。
ある日のことです。
2歳児の子が遊んでいる途中に、床に落ちているおもちゃを見て、「踏んだら危ないから片付けようね。」と言って片付けていました。
ちなみに、この時保育者は誰も片付けを促していません。
床に落ちていると踏んで危ないと気づき、片付けようと思ったのです。
今まで一斉保育をしていた私は、初めて子どもが主体的に動く姿を見てとても驚きました。
この件で、大人がこうさせなければいけないと思わなくても、子どもには自分で学んで動く力があると感じました。
子どもが自分から動いた理由
保育でも子育てでも、子どもが自ら片付けを行う姿はあまり想像できない方が多いと思います。
では、なぜ子どもは自分から片付けをしたのでしょうか。
これは子どもの育ちの仕組みにヒントが隠されています。
「内面化」という言葉を知っていますか?
心理学者のヴィゴツキーによると、子どもは周りの人との関わりから学び、自分のものとして行動できるようになると言われています。
つまり、
- 保育者が「踏むと危ないから、片付けようね」と言いながら片付けるのを見る
- 子どもが「落ちていたら危ないから片付けるんだ」と学ぶ
- 主体的に行動する
このような流れで、子どもが自分から片付ける姿につながったというわけです。
子どもの主体性を育てるには大人が見せることが大切
私は片付けの場面で、主体性を育むためには、大人が色々と言うよりも、実際にやって見せることが大切だと初めて気づきました。
「まだ小さいからわからない」は、意外と大人の思い込みかもしれないと思いました。
子どもは自分の周りで起きていることをよく見て、聞いて、吸収し、学んだことを自分のものにして動いている。
子どもの力を信じてこちらも待たなければいけないと感じました。
保育・育児でもできる関わり方
ここからは、保育・育児でも実践できる関わり方をご紹介します。
子どもが自分で動く力を育む関わり方は、以下のとおりです。
- 大人がやって見せる
- やる理由を伝えていく
- 信じて待つ
どれも特別なことではありませんが、実践すると子どもの自発的な行動につながります。
丁寧な関わりと、子どもを信じる気持ちが「自分で考えて動く力」に変わります。
日々の育児や保育に取り入れて、子どもの生きる力の土台を作っていきましょう。
まとめ:子どもは自分の力で育っていく
いかがでしたか?
子どもは周りにいる人たちからたくさんのことを学び、自分のこととして行動する力を持っています。
大人が色々と指示しなくても、子どもは見て、聞いて学ぶことができるのです。
むしろ、「ああしなさい」と言われるよりも、見て真似て行動した方が、”自分ごと”になりますよ。
子どもの力を信じて、待つこと。そして丁寧な関わりを持っていくこと。
その大切さを知ることのできたエピソードでした。
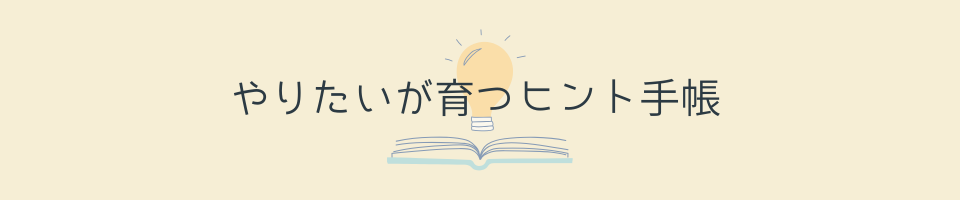
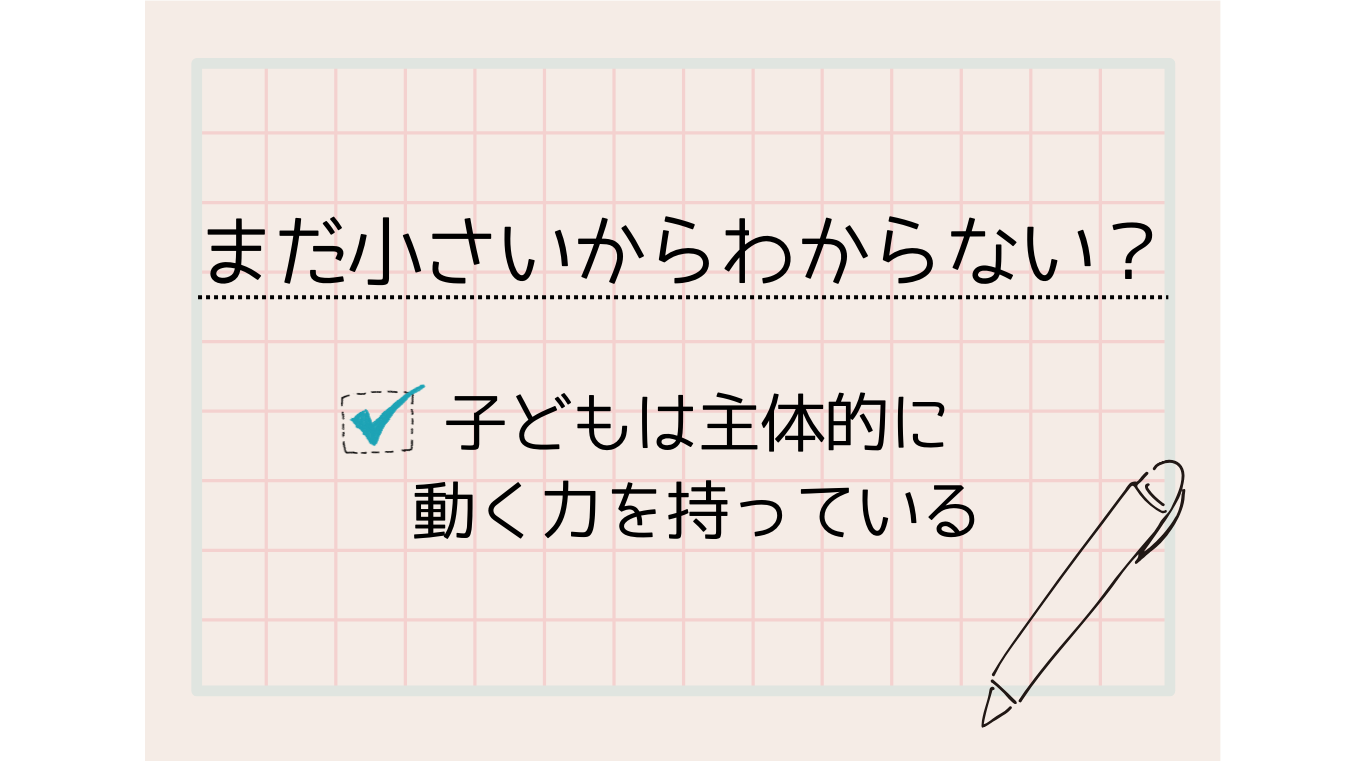


コメント