子どもの様子を見守るとき、私たちは“どこまで手を出すべきか”迷うことがあります。
特にまだ小さな子どもは、挑戦している最中なのか、本当に困っているのかを見極めるのが難しいこともあります。
この記事では、子どもの主体性を尊重する見守りの基本的な考え方や、関わる時の目安をわかりやすく紹介します。
ケース別に見守り方の具体的な例も書いているので、子どもの成長を見守る日々の、ちょうどよい距離感を見つけるヒントになりますように。
主体性保育における“見守る”の基本的な考え方
主体性保育における、『見守る』の基本的な考え方の土台は、子どもの興味や、自分で選んだことを尊重することです。
子ども自身がやりたいことや、やってみたことは、結果が出るまで手を出さずに見守ります。
自分でやってみたいと思って取り組んだとき、決定力や解決力など、子どもの様々な力がぐんと伸びます。
見守る時には、子どもの力を信じることが大切です。「まだ難しいかも」「こうした方がいいから」と思ってしまうかもしれませんが、ぐっとこらえて見るようにしましょう。
「やってみたい!」と思うのは、大好きな先生がいるからこそ。安全で安心できる人の側だからこそ挑戦する気持ちが湧くのです。
子どもにとっての安心・安全の拠点となる意味でも保育者が側で見守る意義があります。
見守るためには、
- 子どもの興味や自分でやろうとしたことを尊重すること
- 信じて待つ姿勢を大切にすること
- 安心・安全の拠点になっていることを理解すること
がポイントになります。
“見守る”と“関わる”の境界線:判断の目安は?
では、関わるべきタイミングとはどんなときでしょうか。以下の3つが判断の目安です。
- 子どもが挑戦しているのか、困っているのかを見極める
- 危険がある場面はすぐに対応する
- 状況によって段階的な関わりをする
関わるタイミングを知り、子どもの主体性の芽を育みましょう。
子どもが挑戦しているのか、困っているのかを見極める
関わるべきか悩んだときには、子どもが挑戦しているのか、困っているのか見るようにしてください。
困っているように見えたら、そっと手を差し伸べるべきです。
たとえば洋服の着脱の場面では、子どもが自分でやろうとしているのか、助けてほしいのか、わかりづらいですよね。
そのため、普段の子どもの様子やその子の発達の具合を把握しておくことが大切です。
子どもの姿をきちんと知っておくと、判断がしやすくなります。
危険がある場面はすぐに対応する
子どもが自分で決めてやっていたとしても、危険がある場合はすぐに対応しましょう。
危険とは、自分や他の子がケガをするおそれがあるときです。
まだ子どもは危ないことの判断ができません。「これはまずいな」と思ったときには即対応するとよいです。
「やりたい気持ちはわかるけど、これは危ないからやめておこうね。」と気持ちは受け止めたうえで止めることがポイントです。さらに、代替案を出せると子どもも納得しやすくなります。
状況によって段階的な関わりをする
子どもにいざ関わろうと思ったときには、状況によって段階的な関わりをすることが望ましいです。
子どもが一人でがんばっているとき、大人はつい「手伝ってあげたい」という気持ちになります。
しかし、すぐに手や口を出してしまうと、子ども自身の挑戦する気持ちを妨げてしまう場合があります。
そこで役立つのが、「段階的な声かけ」です。
例えば、
①共感:「やってみたかったんだね」
②提案:「どうしたらうまくいくか、一緒に考えようか」
③選択肢の提示:「こうする方法もあるよ。どうする?」
といったように、子どもの気持ちを受け止めつつ選択肢を渡すことで、自分で決める経験ができます。
状況に応じて「見守る」「共感する」「提案する」「一緒にやる」など、段階を踏んで関わることで、子ども自身が「自分でやってみよう」という気持ちを持ち続けることができます。
ケース別|どこまで見守る?具体例で解説
例1:片付けをしない子ども

片付けをしてくれません。見守っていていいんでしょうか。
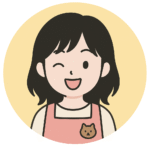
声をかけて片付けを促しはするものの、しなかったら見守っててOK!
片付けがわかってくるのは、大体2歳を過ぎてからなので、それまではこちらが片付けをする姿を見せることが大切です。
ただ片付けるのではなく、「おもちゃがたくさん出ているね。踏むと痛いから片付けよう」「遊ぶスペースがなくなってきたね」などと、理由を添えてから始めましょう。
こうした声かけを重ねることで、「遊ぶ場所がなくなるから片付ける」といった意味が子どもに少しずつ伝わり、自分から片付けようとする姿が見られるようになります。
また、少しでも参加できたときは、しっかり褒めてください。
大好きな先生に認められることは子どもにとって大きな喜びですし、自信や達成感にもつながります。小さな一歩を大事にしていきましょう。
例2:友達とトラブルになりそうなとき

友達とトラブルになりそうな時も見守るのですか?

社会性を学ぶ機会でもあるため、怪我がないように気をつけながら見守りましょう!
乳児では、おもちゃの貸し借りで手が出たり、噛みついたりするトラブルがよくあります。すぐに止める方も多いでしょう。
怪我や事故の心配があれば即対応が必要ですが、そうでなければ少し様子を見るのもひとつです。
衝突を避けようと先に止めたり、「それは〇〇くんが使ってたよ」と保育者が代わりに返してしまうと、子どもが社会性を学ぶ機会を失ってしまいます。
大切なのは、「どこまでが学び」で「どこから助けが必要か」を見極めること。
たとえば、物の取り合いで“取ってしまった側”の子も、「相手が悲しむ」経験を通して学びます。怪我の心配がなければ、取る場面は見守っても構いません。
年齢にもよりますが、悲しんでいる様子を見ても、おもちゃを返す子は少ないものです。子ども同士の解決が難しい場合は、「使いたかったんだね」と気持ちを受け止めつつ、「お友達、悲しそうな顔をしてるね。おもちゃ、使ってたみたい」と助けに入りましょう。
関わるときのポイントは次の通りです:
- 「取ったから悪い」と決めつけず発達や様子を見て判断する
- 「貸してって言う?あとで貸してもらう?」と選択肢を示す
こうした関わりが、子どもの主体性を育てることにつながります。日々の中で、意識してみてくださいね。
例3:やりたい遊びがうまくできずにいるとき

なんだかやりたいことができていません。このまま見守っていると自信をなくすのでは?

それは本当に”困って”いますか?タイミングを見極めて「一緒にやる?」と声をかけるのはアリ!
自分でやりたいことに挑戦している子どもの姿を見ていると、必ずしもうまくいくことばかりではないとわかります。
失敗を繰り返していて、「もうやりたくない!」と自信をなくしてしまうのではないかと心配になりますよね。
だからといって、すぐに「手伝う?」と声をかけるのは、子どもの”考える力”や”失敗してもまたチャレンジしようとする力”を得る邪魔をしてしまうかもしれません。
そのため、“挑戦中”なのか“本当に困っている”のか、子どもの様子を見極める力が必要です。
困っていると感じたら、先ほど書いたように、段階的に関わりを持つのがよいでしょう。
見守る前にすべき3つのこと
これから子どもの主体性を育みたいと思う方に、「見守る」前にするべき3つのことをお伝えします。
- 自分の関わりのクセを振り返る
- 「信じて待つ」姿勢を保育者間で共有する
- 子どもの成長を見守る中で、保育者も学び続ける
見守りを始めていく前に、自分の保育を振り返り全体で同じ眼差しを持てるようにしましょう。
自分の関わりのクセを振り返る
子どもの主体性を伸ばすため、「見守る」関わりを持つ前に、自分自身の関わり方を見直してください。
自分の関わりのクセを振り返ると、見守ることのハードルが下がります。
たとえば、すぐに手を出してしまっている場合は、子どもの力を信じ切れていないことになります。
足りていないのは子どもを見守る姿勢や余裕だということがわかり、環境設定を見直すきっかけとなるかもしれません。
まずは普段の子どもへの関わり方を見直して、見守るための準備を整えましょう。
「信じて待つ」姿勢を保育者間で共有する
信じて待つ姿勢を保育者間で共有することも大切です。保育者によって、関わり方が違うと子どもも、混乱してしまいます。
「信じて待つ」と言っても人によって解釈はそれぞれ違います。異なる解釈のまま保育を進めると、「この先生は待ってくれない・・・」と子どもが先生によって不安を感じる場合があります。
そのため、どのような姿勢か保育者同士で話し合い、明確にすることが必要です。
日中主に関わる保育者だけでなく、時間外(早番や遅番)の人も同じ姿勢で子どもと関われるように意識をすり合わせましょう。
子どもの成長を見守る中で保育者も学び続ける
子どもの成長を見守る中で、保育者も学び続けることを忘れないようにしてください。
日々子どもの姿は変わります。同じような様子の子でも、「あの子にはこの対応がよかったのに、この子にはあまりよくないかも・・・」ということは多々あります。
そのため、保育者が視野を広げる意味でも学び続けることが大切です。本を読んだり、研修に参加したりするとあらたな気づきを得られます。
学んだことを実践して振り返り、再度関わり方について考えていく。このサイクルを自分の中で持っておくと、様々な見守り方が実践できますよ。
まとめ:見守るとは“支えない”ことではない
見守ることと放任は違います。大人が何も言わずに距離を取るだけでは、子どもは「放っておかれた」と感じてしまうこともあります。
つまり、“見守る=何もしない”ではなく、“必要なときに必要なサポートをする”ことが大切です。
安心感のある距離感を大事に、子どもの様子や発達を考慮してどこまで見守るのか見極めたり、関わるときは段階的に声を掛けたりなど、色々なことを考える必要があります。
難しく感じるかもしれませんが、自分の保育を振り返ったり、日々学びながら実践していけば「見守る」コツがわかるようになります。
保育者として、子どもの主体性を信じてそっと寄り添う姿勢を大切にしていきたいですね。
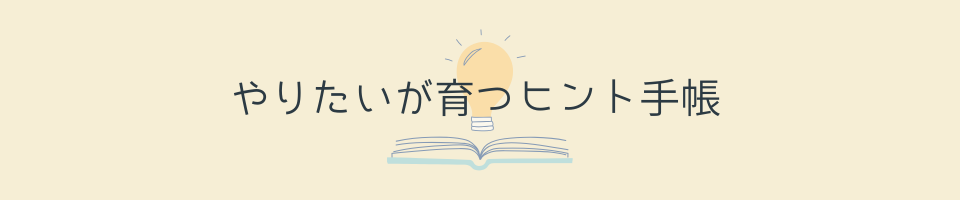
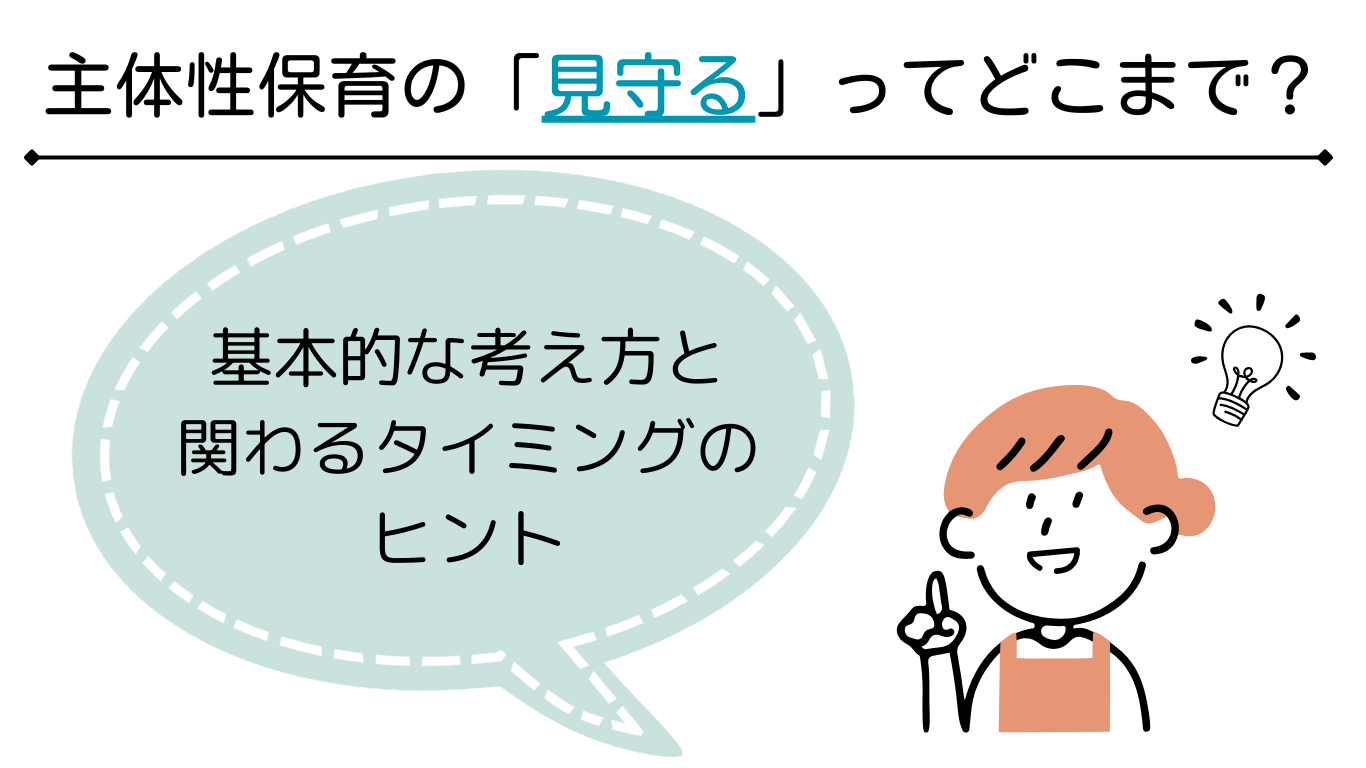


コメント