主体性を育てたいと思うけれど、乳児クラスでもできるの?と疑問に思っていませんか?
結論から言うと、乳児期でも主体性は育てられます!
0〜2歳のうちから主体性を育む関わりをしていくことで、受けた経験が幼児クラスで生きてくるのです。
本記事では、乳児期での主体性についてや、関わるうえで大切にしたいことを紹介します。
主体性を大切にする保育で悩む保育士の方の参考になれば嬉しいです!
主体性とは?乳児期でも育つ力
まずは、主体性についておさらいしましょう。
主体性がある姿とは、子どもが自分で考えて決め、行動する姿を指します。
こちらの記事で詳しく解説しているので、よろしければ見てみてください。
自分で考えて決めると聞くと、乳児にはまだ難しいのではないかと思う方もいるでしょう。
しかし、子どもはどんなときも自分で選択しています。
活動で散歩に行くと決められていても、「行かない」と言う子もいます。
これも実は、立派な子どもの選択です。
0歳児の子でも、自分のやりたい遊び、気になるおもちゃに向かっていきますよね。
大人が思っているよりも、子どもは自分で行動を選ぶ場面が多くあります。
子どもが些細な場面で、自分で決めたことをやり遂げようとする姿を見守り、必要な時に関わりを持つと主体性の芽を育んでいけます。
乳児の主体性を育むために大切にしたい4つの視点
乳児クラスで主体性を育てるための関わりで、大切にしたいことは以下のとおりです。
- 子どもが選べる環境を作る
- 信頼関係を築く
- 思いを汲み取ろうとする姿勢を持つ
- 子どもを1人の人間として尊重する
関わり方のポイントを押さえて、乳児期の子ども達の主体性を育てるお手伝いをしましょう。
子どもが選べる環境を作る
乳児クラスの子どもの主体性を育てるためには、選べる環境を作ることを大切にしてください。
子ども自身が選べる環境を作ると、それぞれの好みやこだわりがわかるようになり、より子ども主体の保育ができます。
まずは、子どもが気になったものに手を伸ばして、取り出せるようおもちゃの配置を工夫するところから始めてみましょう。
集中して遊んでいる子がいたら、集団の中でも安心して遊びこめるように保育者が周囲に声を掛けることも重要です。自分の遊びが守られてきた経験のある子は、ほかの子の遊びも邪魔しません。
年齢や月齢など子どもの様子によっても変わる場合もありますが、「子どもは保育者が関わらないと遊べない」と思い過ぎないことも必要です。思い込みをなくすだけで、過干渉や先回りを防げ、子どもの集中力や発想力を伸ばせます。
環境設定や、関わるときには「子どもにとってどうか」を重視してください。子ども一人ひとりからのサインを丁寧に汲み取り応じていくことが大切です。
信頼関係を築く
信頼関係を築くことは、保育するにあたって欠かせませんが、主体性を育むうえでも重要になります。
信頼関係が築けていると、子どもは安心・安全のもと少しずつ興味関心を広げていきます。自分のやりたいことをしていく中で、子どもは様々なことに挑戦しようとする意欲や、難しいことがあっても諦めずに頑張る力を得られます。
人としての基礎が作られる乳児期では、集団の中で安心して自分を出せて、心が豊かに成長していける場であることが大切です。
「どんな自分でも受け止めてもらえる」と子どもが思えるように信頼関係を築いていきましょう。
思いを汲み取ろうとする姿勢を持つ
主体性を育む関わりで大切なのは、子どもに対してわかろうとするまなざしを持つことです。子どもが表現した思いを受け止めると、生きる意欲を支えられます。
注意してほしいのは、教えようとしないことです。
たとえば、1〜2歳児クラスでは、友達との関わりが出てくる分トラブルも増え、保育者は解決を急いでしまうかもしれません。
しかしそこはグッとこらえて、気持ちに共感し、どうしたらよいのか一緒に考えるようにしましょう。
そうすると、子どもは相手に気持ちがあることを知ったり、困ったときにどうしたらよいかを保育者の対応から学んだりします。
「教える人」ではなく、「助けてくれる人」の立場になることで、子どもが自発的にトラブルにたいしての対処法を獲得することに繋げられるのです。
乳児期の子どもは、言葉がまだ十分でないので、あらゆる方法で自分の思いを表現します。些細な変化に気づき受け止めてあげられるよう、アンテナは敏感にしておきたいですね。
子どもを1人の人間として尊重する
子どもの主体性を育てるのに1番大切なのは、1人の人間として尊重することです。
保育者が子どもを尊重する関わりを持っていくと、「自分の思いをきちんと聞いてくれる」「無理に何かをさせられることはない」と安心感が生まれます。
まずは、「0〜2歳児の子どもは大人がなにかをしてあげないといけない存在」という考えを捨てましょう。
0歳児の子どもでも、自分のあらゆる感覚を使って「この人は自分のことを理解しようとしてくれているか」を感じ取ろうとします。
乳児は五感が非常に敏感で、大人以上に微細な変化に反応する場面もあります。たとえば、母親の声や匂いに反応する力、触れられる心地よさを強く感じ取る力などは、発達初期ならではの特性と言えるでしょう。
子どもを正しく理解しておくと、無言で関わることや、子どもを尊重しない関わりを避けられます。
乳児クラスではつい「やってあげなきゃ」と思ってしまいがちですが、「子どもにとってどうか」を大切に、尊重した関わりを心掛けましょう。
乳児期でも感じた主体性の芽
ここからは、私が実際に「これは、主体性が育っているかも」と感じたエピソードを紹介します。
ここまで見てきても、あまり想像つかないな…という方の参考になれば嬉しいです。
・我が子の主体性の芽生え
我が子は1歳児。ある日、朝ごはんを食べようと誘いかけると、洋服がしまってある棚の方へ走って行きました。
様子を見守っていると、何かを選んでいました。そして納得のいくものが選べると私のところにきて「ばー!(バナナのエプロンのこと)」と言ったのです。
子どもが選んでいたのは、エプロンでした。
朝ごはんを食べる時にはエプロンが必要だということを毎日の習慣から理解し、自分で用意してくれたのです。
このほかにも、子どもはお皿やスプーンも自分で用意してくれます。(たまに使わないお皿も出してくるので、それは理由を言ってしまっていますが…笑)
また、このような姿はほかの場面でも見られています。お風呂の前は、自分が着たいパジャマを持ってきてカゴに入れてくれます。
この姿から主体性が芽生えているなと感じた理由は、こちらが言わなくても、子どもが毎日の習慣をわかって自発的に動いた点です。
まだ1歳児でも、環境を整えたり、関わり方を工夫したりするとこのような姿が見られるんだ、と改めて実感しました。
まとめ:乳児期の関わりが未来の「自分らしさ」を育てる
乳児期でも、主体性を育むことができます。
0〜2歳児クラスでは、子どもの気持ちを受け止めて共感し、「子どもにとってどうか」を大切にした関わりを持つようにしましょう。
「自分は大切にされている」「ここでは安心して自分を出していいんだ」という経験をした子は、幼児クラスでも、その先でもたくましく生きていけます。
ぜひ、乳児の担任になった際は、子どもの主体性を育む関わり方を実践してみてください。
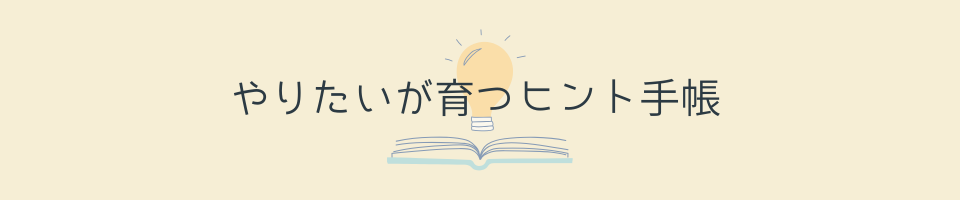
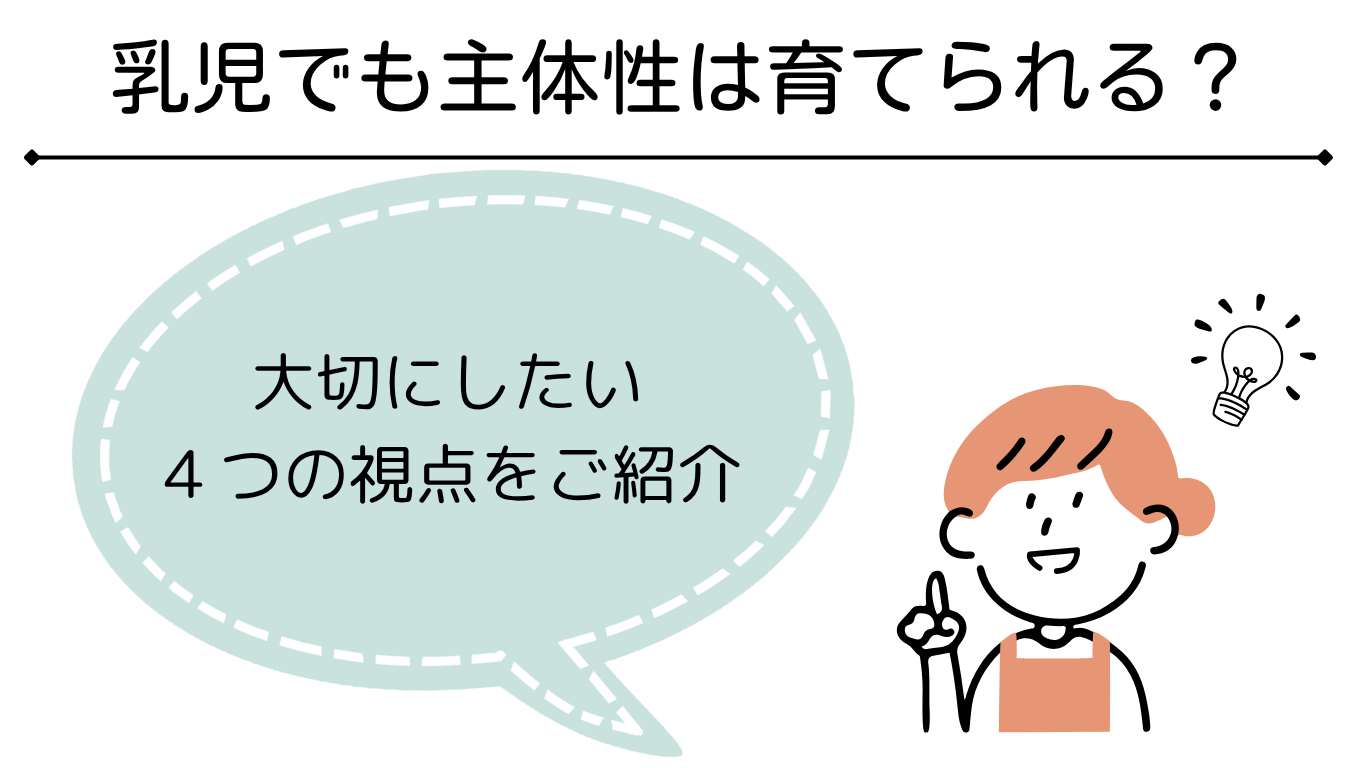

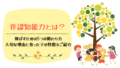
コメント