こんにちは。毎日子どもの姿に寄り添う先生方、お疲れ様です。
9月に入って、徐々に考えていかなければいけない運動会。
でも、主体性保育を実践していると、「行事ってどう考えたらいいの?」「子どもに”やらせて”いいのだろうか。」と悩む方もいるのではないでしょうか。
今回は、主体性保育を学んできた保育士ママのあさのが、主体性保育における行事の考え方 運動会編をご紹介します。
📌この記事でわかること
- 行事(運動会)を主体性保育の視点でどう考えるか
- 乳児・幼児それぞれに合った運動会の考え方
- 子どもの主体性を尊重した行事づくりのヒント
「行事はやらなければいけない」という発想から少し離れて、子どもの姿を中心に据えた運動会のあり方を一緒に考えてみましょう。
「行事」を主体性保育の視点でどう考える?
これまであたりまえのように行ってきた行事ですが、主体性保育の目線で考えると、「行事って必要なのかな?」と疑問を持つ方もいると思います。
過去の私もそうでした。

「子どもにやらせないのであれば、運動会や生活発表会を開催するのって矛盾してないか?」
そう思ったものです。
でも簡単にやめます!とはいかないのが難しいところ。
- 主体性保育で大切なのは「子どもが安心して楽しめる場」
- 行事は誰のためのものか考える
- 子ども・保護者・園それぞれの期待を整理する
以上の3つから、主体性保育における行事のあり方について考えていきましょう。
主体性保育で大切なのは「子どもが安心して楽しめる場」
はじめに、「子どもが安心して楽しめる場であること」が一番大切とお伝えします。
行事は子どもが楽しくなければ意味がありません。ただでさえいつもと違う環境に、不安を感じる子もいるでしょう。
私たち保育士はそれらを踏まえたうえで、
- 行事を行うか
- 行うのであればどのような内容にするか
- 場所などの環境はどうするか
を考える必要があります。
季節ごとに行事があると思いますが、まずは子どもが楽しめているかな?と考えるところから始めてみましょう。
行事は誰のためのものか考える
わかりやすいのは、行事は誰のためにやるのかというところから考えることです。
親を喜ばすための場や、親に子どもの成長を見せる場であるとしたら一度考え直す必要があります。
そのために子どもが何かを練習する、というのはおかしな話です。
やらされるものというのは、子どもにとってはつまらないもの。
練習をするにしても、意欲もわかなかったり、保育園がつまらなく感じてしまったりする場合があります。
運動会や発表会は必ずしもやらなくてはいけないものではありません。
保護者のための行事になっている場合は、子どもを中心にして、運動会のあり方を考えてみましょう。
子ども・保護者・園それぞれの期待を整理する
とはいえ、運動会を楽しみにしている保護者の方も多いです。簡単に、「子どもがやりたくないといっているので止めます。」としてしまっては、理解も得られません。
まずは、子ども・保護者・園それぞれの期待を整理してください。
- 子ども→保護者と安心して楽しみたい、頑張ったことを見てもらいたい
- 保護者→子どもの成長が見たい
- 園→子ども、保護者どちらの思いも汲み取りたい、園でやっていることを保護者に見てもらいたい
上記を踏まえて、運動会をどのような内容にするか考えていきます。
それぞれの期待を踏まえて行事を作っていくと、誰にとってもよいものとなる可能性があります。
保護者に対しても、園の方針を理解してもらう場になるでしょう。
次の項目で詳しく、乳児・幼児別に運動会の目的を紹介します。
乳児・幼児別!運動会の目的
乳児の運動会「その場を楽しむ」
乳児の運動会は、その場を楽しむことを第一に考えましょう。
個人的には、乳児さんには運動会はなくていいと思っています。
なぜなら、乳児さんは環境の変化に敏感です。
場所が変わったり、いつもと違う雰囲気の中で何かをしたりすることは、精神的に負担が大きいと覚えておいてください。
そのため、保護者と一緒に楽しめる競技や、ふれあい遊びがおすすめです。
運動会ではなくスポーツデーのように名前を変更すると、保護者の認識も変わり、変化を受け入れやすくなります。
子どもが安心して楽しめるように、保護者参加の競技を検討してみてください。
幼児の運動会「子どもが主体的に関わる」
幼児の運動会は、「子どもが主体的に関わる」をキーワードに競技を決めていきます。
たとえば、競技決めから子ども達と一緒に考えます。運動会があることを伝えて、お母さん・お父さんに何を見せたいか聞くのです。
子ども達が意見を出し合って競技を決められると、練習への意欲も高められ、主体的に参加することが期待できます。
自分たちで決めてやり遂げることができれば達成感を感じ、自信へとつなげていけますよ。
子ども主体で行事を考える4つの視点
では実際に子ども主体で行事を進めていこうとした時に、どのような視点を持って子どもと関わっていけばよいかを紹介します。
- プロセスを楽しむ
- 多様な役割を用意する
- 小さな達成感を積み重ねる
- 保護者への伝え方を工夫する
実践してみようと思ったときの参考になれば嬉しいです!
プロセスを楽しむ
子どもを真ん中にして考えるのであれば、運動会までの過程を楽しめるようにしましょう。
練習や準備も子どもの主体性を育む場となります。
どのように練習をするのか、なにを準備するのか子どもと決めていくことで、子どもは「自分が運動会に関わっている」という実感を持てます。
たとえば、道具をどこに置くか、順番をどうするか、どの役割をやりたいかなど、些細なことでも自分で考える経験は主体性につながります。
また、うまくできなくても挑戦する過程を一緒に喜び、励ますことで、子どもは「やってみてよかった」と感じられます。
こうした積み重ねが、運動会当日の達成感や自信につながり、結果だけでなくプロセスそのものを楽しめるようになるのです。
多様な役割を用意する
運動会に参加したくない子もいるかと思われます。そのような場合は、多様な役割を用意して、準備や応援などの形で関われるように工夫してください。
たとえば、たくさんの人の前に出るのが苦手、競うのが得意ではないという子もいるでしょう。
様々な役割があると知ると、「これなら自分も運動会を頑張れるかもしれない」と参加への意欲へ繋げられる場合があります。
子どもにどんなことならできるか聞いて役割を一緒に考えることもおすすめです。
無理なく参加できた経験は、「ありのままの自分でいいんだ」と感じることができ、子どもの自己肯定感を高められます。
小さな達成感を積み重ねる
運動会の準備や練習は、本番の結果だけがすべてではありません。
日々の遊びや活動の中で、子どもが「できた!」と感じる瞬間を大切にすることが、主体性を育む鍵です。
たとえば、縄跳びや跳び箱など、遊びの延長でできることが増えたら、一緒に喜びを共有しましょう。
その小さな成功体験の積み重ねが、当日の意欲や自信につながります。
保護者への伝え方を工夫する
運動会で、子どもたちが全員、練習通りにできるとは限りません。
そのときに大切なのは、子ども一人ひとりの「その子らしさ」を認めることです。
保護者には、プログラムやお便りを通して「当日うまくいかなくても大丈夫。練習や日々の成長を見てほしい」というメッセージを伝えましょう。
ドキュメンテーションを活用するのもよいですね。
そうすることで、保護者も子どもの主体性や個性を理解し、安心して見守ることができます。
まとめ:行事は「子どもまんなか」で考えよう
💡 ポイント
- 「誰のための行事か」「子どもにどんな経験をしてほしいか」を整理する
- 乳児・幼児の特性に合わせて競技や関わり方を考える
- 練習・準備・当日までを主体性を育むプロセスとして捉える
運動会は、必ずしも「やらなければいけないもの」ではありません。
大切なのは、子どもが安心して楽しめる場であること、そして子どもの主体性を尊重することです。
行事の目的を明確にし、子どもの姿を中心に据えて考えることで、運動会は「やらされる行事」ではなく、子どもも保育士も保護者もみんなが安心して楽しめる場になります。
ぜひ記事を参考に、運動会をはじめとした行事を見直してみませんか?
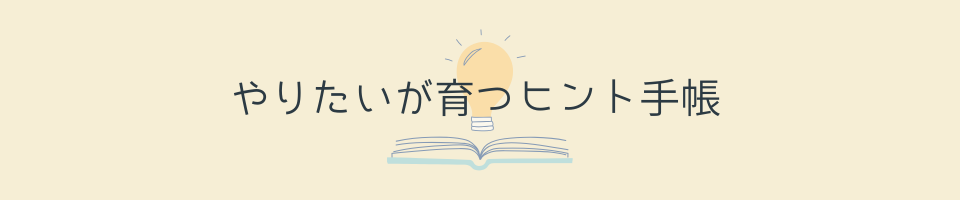
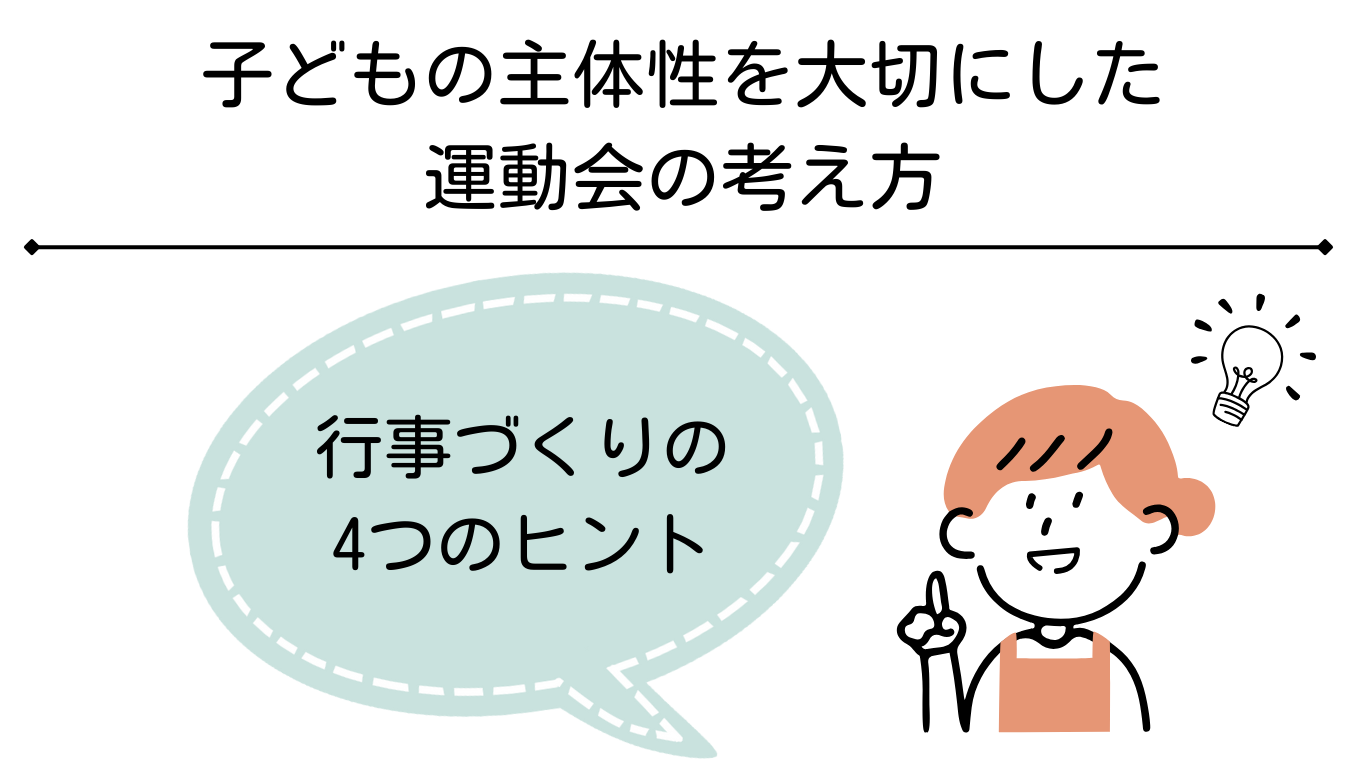
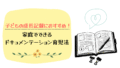
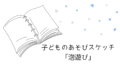
コメント
ちささん、記事を拝読しました。
運動音痴だったんで、運動会で活躍できなかったんで、逆走とかしてめだとうとしてたのを思い出しながら読んじゃいました。
運動会で先生や親に怒られたことがあるのは希少種だと思いますが、開催する側も色々と考えなきゃなんですね。
子供の小さな達成感を積み重ねるという言葉に、なんか胸が熱くなっちゃいました。
素敵な記事を読ませていただいて感謝です。
マサキさん、ありがとうございます!
運動会で怒られる・・・というのは実はあるあるだったりします。
保育園でも幼稚園でも、きれいに、揃って「見せる」ことがよいとされている文化があるのは事実です。
(文化と言ってはなんですが・・・)
子どもそれぞれ得意・不得意はありますから、全員が同じ目標ではなく、個々の目標に合わせて成功を積み重ねていけるといいなと思っています!